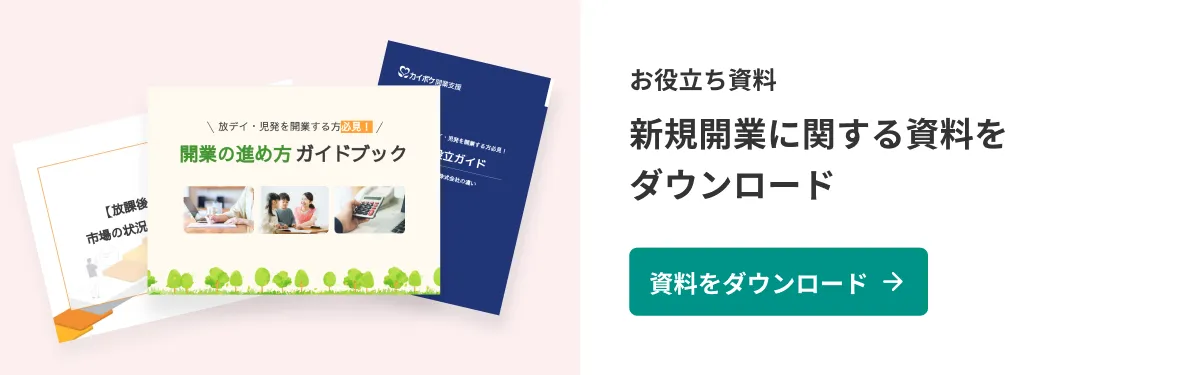【2024年最新】児童発達支援の人員配置基準とは?
SMS CO.,LTD
児童発達支援を開業・運営するにあたり、児童発達支援管理責任者や児童指導員など、満たすべき人員の配置基準が定められています。
今回は、開業時に必要な人員配置基準や人員配置基準を満たす際の注意点を解説します。
放デイ・児発の開業でお困りなら「カイポケ開業支援」
カイポケ開業支援は、初期費用・サポート費用0円で専任スタッフが開業をお手伝いします!
開業までのスケジュールのご案内や、指定申請などの複雑な手続きをサポート。
開業をご検討中の方は、資料をダウンロードして詳細をご確認ください。

目次
- 児童発達支援の人員配置基準とは?
- 職種ごとの概要と資格要件
- 児童発達支援の人員配置基準を満たす際の注意点
- 児童発達支援事業所と児童発達支援センターの人員配置基準の違い
- 児童発達支援の開業は『カイポケ開業支援』にお任せください!
- まとめ
児童発達支援の人員配置基準とは?
児童発達支援事業には児童発達支援センターと児童発達支援事業所(センター以外)の2通りがあります。
ここでは児童発達支援センター以外の事業所における人員基準について説明していきます。
※児童発達支援センターとの違いについては4項で説明します。
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外)人員基準
児童発達支援では、事業を行うために最低限配置しなくてはいけない職種・人員が定められており、主として重症心身障害児以外を通わせる事業所では、以下の人員配置基準を満たさなくてはなりません。
| 職種 | 配置人数・要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人以上 | 他業務との兼務可 |
| 児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 1人以上は専任・常勤 |
| 児童指導員または保育士 | 利用定員10名まで:2人以上
利用定員11名~15名:3人以上 利用定員16名~20名:4人以上 ※利用定員が、5またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上 |
児童指導員または保育士のうち1人以上は常勤でなければならない。 |
| 機能訓練担当職員 | - | 必要な場合にのみ配置 |
| 看護職員 | - | 必要な場合にのみ配置 |
開業に興味をお持ちの方は、こちらから資料をダウンロードください。
職種ごとの概要と資格要件
管理者
管理者は、職員及び業務の管理を行う職種で、事業所ごとに1人以上の配置が必要です。
具体的には、職員の育成や労務管理、事業所の環境整備、広報や営業活動等を行います。
また管理者は管理業務に支障がない場合、当該事業所の他の職務や当該事業所以外の事業所の職務を兼務することが可能です。
管理者の資格要件
管理者として働くために必要な資格等はありません。
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、個々のサービス利用者について、アセスメントや個別支援計画の立案などを行います。その後の定期的な評価を行うなど、一連のサービス提供プロセスにおける責任者となります。
児童発達支援管理責任者の資格要件
児童発達支援管理責任者は以下の要件を2点満たす必要があります。
①実務経験の要件を満たす
下記いずれかの実務経験が必要となります。
| 項目 | 経験年数 | 必要な実務経験や保有資格 |
|---|---|---|
| 相談支援業務 | 5年以上かつ老人福祉施設等以外での実務経験が3年以上 | 障害児相談支援事業等の施設等、保健医療機関、障害者職業センター等、学校等における相談支援業務の経験 |
| 直接支援業務 | 8年以上かつ老人福祉施設等以外での実務経験が3年以上 | 障害児入所施設・障害児通所支援事業等の施設、医療機関等における介護業務、重度障害者多数雇用事業所等における就業支援業務、学校等における直接支援業務等の経験 |
| 有資格者 | 5年以上かつ老人福祉施設等以外での実務経験が3年以上 | 保育士、児童指導員任用資格、介護職員初任者研修、
社会福祉主事任用資格などの資格を有し、かつ直接支援業務に従事した経験 |
| 国家資格 | 5年以上かつ相談支援または直接支援業務の経験が3年以上 | 社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士などの国家資格に関する業務に従事した経験 |
②基礎研修修了後にOJTを経て、実践研修を修了する
| 項目 | 主な内容と受講条件 |
|---|---|
| 基礎研修 | ・児童発達支援管理責任者としての基本姿勢やサービス提供のプロセス、個別支援計画の作成方法等を学習する。
・研修時間は約26時間で、実務経験の要件を満たす2年前から受講可能。 |
| OJT | ・基礎研修修了後に、原則2年以上のOJT(実務経験)が必要。
・特定の条件を満たす場合は6カ月以上に短縮。※1 |
| 実践研修 | ・OJTの実施に加えて、過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務に従事した経験がある場合、実践研修の受講が可能。
・障害福祉の動向や人材育成、多職種連携についての研修を約14.5時間受講。 |
※1特定の条件は以下の通りです。
①基礎研修受講時に既に実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3〜8年)を満たしている。
②障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。
③上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。
参考資料:サービス管理責任者等に関する告示の改正について
児童指導員または保育士
児童指導員または保育士は、個別支援計画に基づき、児童の自立支援と日常生活の指導、訓練等を行う職種です。
児童指導員の資格要件
児童指導員として働くには、任用資格を証明する書類(卒業証明書や実務経験証明書)が必要です。また任用資格を得るには、下記いずれかの条件に該当している必要があります。
任用資格の主な条件
- 児童福祉施設の職員の養成学校・施設の卒業
- 社会福祉士・精神保健福祉士の資格
- 大学や大学院にて社会福祉学等の課程を履修し卒業
- 高校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事した経験
- 幼稚園、小・中・高等学校等の教諭となる資格
- 3年以上児童福祉事業に従事した経験
機能訓練担当職員
機能訓練担当職員は、個別支援計画に基づき、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う職種です。当該施設において、機能訓練を行う場合のみ必要とされます。
また専従の機能訓練担当職員は、児童指導員または保育士の合計数に含めることができます。
機能訓練担当職員の資格要件
機能訓練担当職員として働くには、下記いずれかの資格が必要となります。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 心理担当職員等(臨床心理士、公認心理士等)
児童発達支援の人員基準を満たす際の注意点
ここでは行政による運営指導等で指導の対象とならないために、人員配置基準を満たす際の注意点について解説します。
常勤とみなされる時間について
常勤とは、当該事業所において定めている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達している従業者を指します。
常勤の従業者が勤務すべき時間数が1週間に32時間を下回る場合は、1週間に32時間を基本として、常勤か非常勤かを判断することになります。
ただし、育児による勤務時間短縮等の場合については、「常勤の従業者が勤務すべき時間数」を1週間に30時間として取り扱うことが認められています。
児童発達支援管理責任者の兼務は可能?
児童発達支援管理責任者は、管理者との兼務は可能ですが、児童指導員や保育士との兼務はできません。
ただし、児童発達支援管理責任者の業務に支障が出ない範囲において、直接支援を提供することも差し支えないが、その場合であっても指定基準上必要とする児童指導員等の員数に算定することはできない、とされています。
人員基準を満たさなかった場合に処置される事
人員欠如の場合は 減算 があるので注意してください。
①サービス提供職員欠如減算
サービスの提供単位に人員が欠如している場合は、人員基準が満たされるまでの間、基本的に 単位数の30%が減算 されます。
→1割を超える欠如:翌月から減算
→1割未満の欠如:翌々月から減算
②児童発達支援管理責任者欠如加算
人員基準が満たされるまでの間、基本的に 単位数の30%が減算 されます。
※このため、児童発達支援管理責任者は有資格者の少ない職務なので人事管理に十分注意する必要があります。
児童発達支援事業所と児童発達支援センターの人員配置基準の違い
児童発達支援事業所と児童発達支援センターは、障害児が自宅などから通所して、日常生活動作に関する知識や技能の修得や集団生活に適応できるように療育や支援を受けるという共通の定義があります。
その違いは 「専門性」 になります。
① 児童発達支援事業所と児童発達支援センターの違い
児童発達支援センター
通所による障害児の支援の他に、 専門家の配置や専門機能 を活かし、地域の障害児や家族への相談援助、他の障害児を預かる施設への助言や援助を行うなど、地域で障害児療育に関わります。
児童支援発達事業所
目的は、施設を利用する障害児に対する療育やその家族に対する支援を行うことです。
② 児童発達支援事業所と児童発達支援センターの人員基準の違い
児童発達支援センターの人員基準について児童発達支援事業所と比較してみましょう。その専門的機能の違いがわかります。
児童発達支援センターの人員基準(札幌市)
※児童発達支援事業所の人員基準と異なる点を記載
- 嘱託医1名以上
主たる障害区分に基づいた専門医の配置
例:知的障害や精神科または小児科の診療に相当する経験 - 児童指導員および保育士
児童指導員および保育士の総数は、指定児童発達支援単位ごとに各1名以上通じ、おおむね障害児の数を4で除して得た数 - 栄養士および調理師
40名以下の指定事業所は、栄養士を置かない事が出来る。
各1名以上。
調理業務を全部委託する指定事業所は、調理師を置かない事が出来る。
主として難聴児が通所する事業所において配置
- 言語聴覚士
指定発達単位ごとに4以上 - 機能訓練担当職員
機能訓練指導員は日常生活を行うに必要な機能訓練を行う場合に必要数を配置
主として重症心身障害児が通所する事業所において配置
- 看護師1名以上
- 機能訓練担当職員1名以上
※機能訓練担当職員、言語聴覚士および看護師は、児童指導員および保育士の総数に含める事ができる。
児童発達支援の開業は『カイポケ開業支援』にお任せください!
児童発達支援の開業には、半年から1年ほどの準備期間が必要になります。そして、この開業準備期間に、法人設立や指定申請といった行政手続き、物件・備品等の手配、職員の採用などを行わなければなりません。
『カイポケ開業支援』では、行政手続きに関する情報提供や開業スケジュールの作成など、開業に必要な様々なサポートを無料で提供しています。
「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集では分からないことが多い」といった悩みをお持ちの方は、こちらからカイポケ開業支援へご相談ください。
まとめ
今回は、児童発達支援の人員基準について解説しました。必要な人員数や職種などそれぞれに関して規定があるため、間違いのないよう基準を確認しましょう。
また、指定申請にあたっては都道府県または市区町村等に事前相談が必要な自治体が多いので、指定申請のまえに管轄の自治体に問い合わせたうえで準備を行いましょう。
関連記事:
放デイ・児発の設備基準は?
放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請とは?
※さらに詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからダウンロードできます