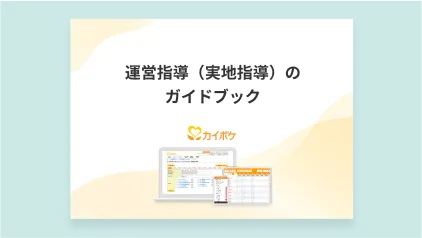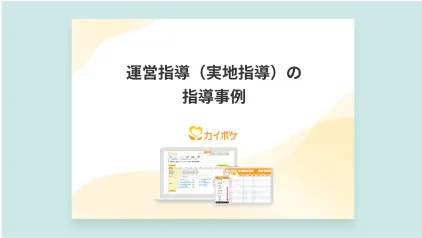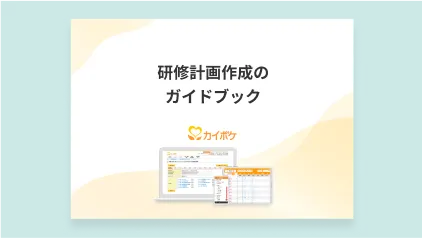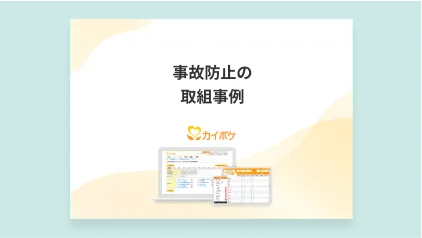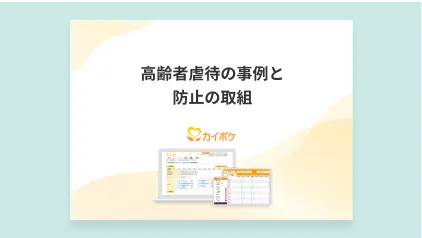介護事業所・施設のBCP(業務継続計画)策定・運用・研修を一挙に解説!
現在、介護事業所・施設においてBCP(業務継続計画)の策定は義務化されています。
これから事業所を開業する方や、作成したBCPの見直しを検討している方の中には「何から手を付ければいいか分からない」、「研修って何をすればいいの?」、「どういうふうに見直しをすればいいの?」と悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、介護事業所・施設におけるBCPについて、基礎から策定・運用のポイント、記載項目や留意点、研修・運用・見直しまで、詳しく説明していきます。
目次
- 介護事業所におけるBCP(業務継続計画)とは?
- BCP策定の義務化と業務継続計画未策定減算
- 適切にBCPを策定・運用する5つのメリット
- 感染症BCP・自然災害BCPの策定・運用のポイント
- 感染症BCPに記載すべき項目
- 感染症BCPの留意点
- 自然災害BCPに記載すべき項目
- 自然災害BCPの留意点
- 厚生労働省のひな型や解説動画
- BCP策定後に行う研修の例
- BCP策定後に行う訓練の例
- まとめ
介護事業所におけるBCP(業務継続計画)とは?
BCP(ビー・シー・ピー)とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画と訳されます。
自然災害や感染症のまん延といった緊急事態に備え、企業や団体が事業を継続するためにどのように行動するか、具体的な指針等を定めた計画のことです。
昨今の自然災害の増加や感染症のまん延から、災害や感染症が発生した場合であっても、介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、介護事業所・施設には、業務継続計画の策定が義務付けられています。
BCP策定の義務化と業務継続計画未策定減算
2024年度の介護報酬改定により、BCP(業務継続計画)を策定していないことへのペナルティとして「業務継続計画未策定減算」が創設されました。
2025年3月31日までは経過措置期間でしたが、現在はBCP(業務継続計画)が未策定である場合、減算が適用になります。
業務継続計画未策定減算の単位数、適用要件は以下です。
単位数
- 施設・居住系サービス:所定単位数×3%の減算
- その他のサービス:所定単位数×1%の減算
適用要件
以下の要件を満たしていない場合に減算が適用になります。
- BCP(業務継続計画)を策定し、業務継続計画に従い、必要な措置を講じている。
なお、BCPの周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の適用要件ではありません。
適切にBCPを策定・運用する5つのメリット
ここでは適切にBCPを策定し、運用するメリットを5つご紹介します。
法令遵守と減算の回避
これまでも説明してきたように、介護事業ではBCPの策定が義務付けられており、策定・運用していないと、行政から指導を受けることになり、業務継続計画未策定減算が適用になる場合があります。
そのため、適切にBCPを策定・運用することで、法令を遵守でき、また、経営状況に影響する減算を回避できるというメリットがあります。
利用者様を守ることに繋がる
BCPを策定することで、災害や感染症が発生した場合に速やかに対応できるようになり、利用者様の健康や生活を守ることができるというメリットがあります。
従業員を守ることにも繋がる
BCPの策定により、災害等発生時の担当者、優先業務、対応範囲などを明確にしておくことで、過度な労働負担を防止でき、従業員の安全を守ることができるというメリットがあります。
経営への影響の最小化
BCPを策定・運用することは、事業の継続と事業を中断した場合の早期の再開に役立つので、経営・事業活動への影響を最小化できるという点でもメリットになります。
地域への貢献にもなる
BCPを策定し、事業所・施設が災害や感染症が発生した場合に事業を継続し、福祉避難所等として活動できることは、地域貢献という点でメリットがあります。
また、災害等の発生に備えて、日ごろから地域とのコミュニケーションを取ることは、地域との信頼関係の構築に繋がります。
感染症BCP・自然災害BCPの策定・運用のポイント
ここからは、厚生労働省が公開している「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」および、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」を参考に、策定、運用のポイントについてご説明します。
感染症BCP・自然災害BCPの策定・運用に共通するポイント
感染症BCP・自然災害BCPの策定・運用に共通するポイントとして以下の3点が挙げられます。
正確な情報集約と判断ができる体制を構築する
災害発生時や感染(疑い)者発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制、情報伝達フロー等の構築がポイントとなります。そのためには、以下の事項を明確にしましょう。
- 全体の意思決定者を決めておく
- 各業務の担当者を決めておく(誰が、何をするか)
- 関係者の連絡先、連絡フローを整理しておく
業務の優先順位を整理する
施設・事業所や職員の被災状況、感染状況によっては、限られた職員・設備でサービスの提供を継続しなければならないケースも想定されます。
そのため、職員の出勤状況、被災状況に応じて対応できるよう、業務の優先順位を整理しておくことが重要です。
計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練を行う
BCPは、策定すれば終わりではなく、不測の事態が発生した時、迅速に行動できるように、関係者に周知し、平時から研修や訓練(シミュレーション)を行うことが求められています。
机上で設定した内容だけでは実際に災害等が起きた時に、計画通りに行動することは難しいので、平時に訓練等を行い、どのような行動を取るのかを周知しましょう。
また、研修や訓練を行ったなかで課題を発見した場合は、より良いBCPになるように更新しましょう。
感染症BCP策定・運用のポイント
感染症BCPを策定するためのポイントとして以下のようなことが挙げられます。
職員の確保
職員が感染者となってしまった場合、職員が不足する場合があります。
感染者と非感染者の入所者・利用者へのサービス提供の際は、可能な限り担当職員を分けることが望ましいとされます。
しかし、職員が不足した場合、こうした対応が困難となり、感染拡大のリスクが高まります。
そのため、施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県等への応援依頼などについても定めておきましょう。
自然災害BCP策定・運用のポイント
自然災害BCPでは「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて、それぞれの対策やルールを決めましょう。
自然災害への「事前の対策」
- 設備・機器・什器を耐震固定しておく
- インフラが停止した場合のバックアップを備えておく
自然災害の被災時の対策
- 人命安全のルール策定と徹底
- 事業復旧に向けたルール策定と徹底
- 初動対応
- 利用者・職員の安全確保・安否確認
- 建物・設備の被害点検
- 職員の参集
感染症BCPに記載すべき項目
厚生労働省が公開している「感染症ひな形(入所系)」によると、入所系の感染症BCPに記載すべき項目は以下の通りです。
※訪問系の感染症BCPに記載すべき項目はこちらの記事をご覧ください。
※通所系の感染症BCPに記載すべき項目はこちらの記事をご覧ください。
| 分類 | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1.総則 |
|
- |
| 2.平常時の対応 |
|
- |
|
|
|
| 3.初動対応 |
|
- |
|
|
|
| 4.感染拡大防止体制の確立 |
|
- |
|
|
感染症BCPの留意点
感染症BCPを策定するうえで特筆すべき点や留意したい点について、介護サービス類型を入所系、通所系、訪問系に分けてご説明します。
入所系サービスにおける留意点
入所系サービスは、入所者に「生活の場」を提供しているため、サービスの提供を継続しながら施設内での感染拡大をいかに防ぐかという点に留意しましょう。
感染疑い者への対応
- 個室管理の原則:感染疑い者は個室へ移動させます。個室が不足する場合は、マスク着用を求め、ベッド間を2m以上空けるかカーテンで仕切ります。
- 対応職員の選定:感染疑い者とその他の入所者で可能な限り担当職員を分けます。
- 施設内での検体採取:保健所の指示により施設内で検体採取を行う場合、他の入所者と動線が交差しない場所を選定し、換気・清掃・消毒を徹底します。
- 体調不良者の確認:感染疑い者と同室の入所者や接触機会の多い利用者を中心に体調不良者の調査を行います。
- 消毒・清掃:感染疑い者が利用した居室や共有スペースの高頻度接触面を消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液で清拭します。噴霧は行いません。
感染拡大防止体制の確立
- 接触者への対応:濃厚接触者に対しても、原則個室対応。有症状の場合は速やかに別室へ、個室不足時は症状のない者同士を同室にするか、2m以上の間隔を空ける等の対応を行います。
- 担当職員の選定:接触者の介護も可能な限り担当職員を分け、基礎疾患のある職員や妊婦には勤務上の配慮を行います。
- 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング):清潔区域と不潔区域を明確に分け、人や物の出入りを制限し、担当職員を決めます。感染者がいるエリアから出さない、専用トイレを設けるなどの対応を行います。
- 職員の確保:勤務可能な職員と休職が必要な職員を把握し、シフト管理を行います。同一法人内からの支援、近隣事業所からの人員確保も検討します。看護職員の連携も重要です。委託業者が対応困難な場合も想定します。
- 業務内容の調整:業務を重要度に応じて分類し、職員の出勤状況に合わせて提供サービス(食事、排泄、医療的ケア、清拭など)の優先順位を検討し、絞り込みや手順変更を行います。
通所系サービスにおける留意点
通所系サービスは、多数の利用者が集まる「通いの場」であるため、事業を継続するか、一時的に休業するかの判断に留意しましょう。
感染疑い者の発生
- 送迎時の体温計測:送迎車に乗る前に利用者・家族または職員が体温を計測し、発熱がある場合は原則利用を見合わせます。
- 利用休止の判断:利用者が体調不良の場合は事業所へ電話連絡を依頼し、管理者へ連絡して判断を仰ぎます。
初動対応
- 感染疑い者への対応:利用者の利用を一旦休止し、居宅介護支援事業所と連携して代替サービスの確保・調整に努めます。
- 消毒・清掃:感染疑い者が利用した共有スペース(出入口、デイルーム、座席、テーブル、トイレ等)の高頻度接触面を消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム液で清拭します。噴霧は行いません。
休業の検討
- 休業基準の明確化:感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員数、消毒状況などに応じて、休業を検討する指標を明確にします。
- 訪問サービスの実施検討:利用者のニーズや対応可能な職員に応じて、訪問サービスの実施を検討します。
- 居宅介護支援事業所との調整:業務停止日、再開日、休業中の対応について情報提供し、代替サービス確保に努めます。
- 利用者・家族への説明:休業期間、事業所窓口、消毒状況、再開基準などを説明します。
感染拡大防止体制の確立
- 接触者への対応:濃厚接触者の利用者は自宅待機とし、居宅介護支援事業所と調整して生活に必要なサービスを確保します。
- 利用者への再開支援:「利用控え」が生じる可能性があるため、ケアマネジャーと連携して健康状態・生活状況の確認、代替サービスの検討を行い、感染防止対策を説明することで利用再開を働きかけます。
訪問系サービスにおける留意点
訪問系サービスでは、利用者の自宅というプライベートな空間でサービスを提供するため、利用者や家族の協力を得ながら、感染対策を徹底した上でサービスを継続することに留意しましょう。
感染疑い者への対応
- サービス提供の検討:居宅介護支援事業所等と連携し、サービスの必要性を再度検討した上で、感染防止策を徹底してサービス提供を継続します。
- 担当職員の優先順位:可能な限り担当職員を分けて対応するか、最後に訪問する等の対応を行います。
感染拡大防止体制の確立
- 接触者への対応:居宅介護支援事業所等を通じて保健所とも相談し、生活に必要なサービスを確保し、訪問介護等の必要性を再検討します。利用者の自宅での手洗い・うがい、換気の環境整備と家族の理解・協力が重要となります。
- 担当職員の制限:当該利用者へ対応する職員の数を可能な限り制限するよう努めます。
- 業務内容の調整:居宅介護支援事業所や関係機関等と相談した上で、訪問時間を可能な限り短くするなど、感染防止策に留意した上でサービス提供を行います。
- 優先業務の明確化:優先的にサービスを提供すべき利用者を事前にリストアップし、優先度に応じたサービスを提供できるよう「災害時利用者一覧表」などを活用します。
自然災害BCPに記載すべき項目
厚生労働省が公開している「自然災害ひな形(共通)」を参考にすると、自然災害BCPに記載すべき項目は以下の通りです。
| 分類 | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1.総論 |
|
- |
|
- | |
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.平常時の対応 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.緊急時の対応 |
|
- |
|
- | |
|
- | |
|
- | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.他施設との連携 |
|
|
|
|
|
| 5.地域との連携 |
|
|
|
|
自然災害BCPの留意点
自然災害BCPを策定するうえで特筆すべき点や留意したい点について、介護サービス類型を入所系、通所系、訪問系に分けてご説明します。
入所系サービスにおける留意点
入所系サービスは、入所者にとって「生活の場」であるため、施設が被災したとしてもサービスの提供を中断できないという特性に留意しましょう。
災害発生後、外部からの支援が届くまで自力で事業を継続できるように備蓄(食料、水、衛生用品、感染対策物資など)も考慮します。
平時からの対応
- サービスの継続:被災時に最低限のサービスを提供し続けられるよう、自施設でのサービス提供と他施設への避難の両方を想定して準備を進めます。
災害発生時の対応
- 避難方法:津波や水害の危険がある場合は、建物内の高所へ避難する「垂直避難」を検討し、場所と誘導方法を具体的に定めます。エレベーターが使用できない場合の避難方法も考慮します。
- 職員の休憩・宿泊場所:職員が長期間帰宅できない場合に備え、施設内の会議室や食堂の一部、または近隣のホテルなどを休憩・宿泊場所として確保します。
- 福祉避難所の運営:自治体から福祉避難所の指定を受けている場合、受入可能人数、場所、期間、条件、支援人材の確保(ボランティア受入方針等)について具体的に計画します。指定がない場合でも、要援護者や近隣住民の受入要望に対応できるよう準備することが望ましいです。
- 優先業務の具体例(出勤率30%時):食事(災害時メニュー、朝夕のみ)、排泄(オムツ利用)、医療的ケア(必要最低限)に絞り込みます。入浴、機能訓練、洗顔、洗濯、清掃などは休止または限定的に行います。
通所系サービスにおける留意点
利用者が日中に来訪する「通いの場」であるため、災害発生(または予見)時の利用者の安全確保と、安全な帰宅支援が重要となります。
平時からの対応
- 安全確保方法や緊急連絡先:サービス提供中に被災した場合に備え、利用者への安否確認方法や緊急連絡先(複数手段)を居宅介護支援事業所と連携して整理します。地域の避難方法や避難所情報にも留意し、地域関係機関との良好な関係構築に努めます。
災害が予想される場合の対応
- サービスの休止・縮小の判断:台風などで甚大な被害が予想される場合は、サービスの休止・縮小の基準をあらかじめ定め、利用者や家族、居宅介護支援事業所に説明します。必要に応じてサービスの前倒しも検討します。
災害発生時の対応
- 長期休止時の代替サービス:サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、他事業所の訪問サービス等への変更を検討します。
- 利用者帰宅支援:利用中の被災時は、利用者の安否確認後、緊急連絡先を活用して家族へ連絡し、安全確保と帰宅支援を行います。送迎車が困難な場合は、事業所での宿泊や近くの避難所への移送も検討します。
訪問系サービスにおける留意点
職員が利用者の自宅を訪問するサービス形態のため、広範囲に点在する利用者と、移動中の職員の安全確保に留意しましょう。
平時からの対応
- 安全確保方法や緊急連絡先:サービス提供中に被災した場合に備え、利用者への安否確認方法や緊急連絡先(複数手段)を居宅介護支援事業所と連携して検討します。職員が利用者宅訪問中または移動中であることも想定し、対応手順をあらかじめ検討しておくことが重要です。地域の避難方法や避難所情報にも留意し、地域関係機関との良好な関係構築に努めます。
災害が予想される場合の対応
- サービスの休止・縮小の判断:台風などで甚大な被害が予想される場合は、サービスの休止・縮小の基準をあらかじめ定め、利用者や家族、居宅介護支援事業所に説明します。必要に応じてサービスの前倒しも検討します。
災害発生時の対応
- 長期休止時の代替サービス:サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、他事業所の訪問サービス等への変更を検討します。
- 職務中の利用者支援:あらかじめ検討した対応方法に基づき、利用者宅訪問中または移動中の職員は、利用者への安否確認や支援を行います。
- 避難先でのサービス提供:居宅介護支援事業所や地域の関係機関と連携し、可能な場合には避難先においてサービスを提供することを検討します。
厚生労働省のひな型や解説動画
厚生労働省がこちらのページで各種ひな型や解説動画を公開しています。
BCP策定の際はぜひ参考にしてください。
BCP策定後に行う研修の例
BCPは策定して終わりではなく、定期的に研修や訓練を行うことで、災害時に実際に行動できるようになります。
具体的な研修の例として、以下のような研修が紹介されていますので、ぜひ事業所・施設で実施する研修に含めましょう。
(1)防災意識の啓蒙
最近の事例共有などで災害への理解を深めます。
(2)自宅の防災
家庭の防災を教育します。
例:家具の転倒防止、水・食料の備蓄など
例:内閣府 【防災シミュレーター】
(3)ルールの徹底
参集基準や行動基準について周知を行います。
- 参集基準:ルールを教えます。できれば、携帯カードなどを携帯します。
- 行動基準:ルールを教えます。グループ討議なので、具体的な課題を話し合います。
(4)安否確認の徹底
災害発生時の安否の連絡手段を教えます。できれば、複数の通信手段を考えるのが望ましいです。伝言ダイヤルなどの使い方は、携帯カードに記載します。
BCP策定後に行う訓練の例
(1)参集訓練(対策本部員向け)
夜間、休日を想定し、対策本部員が事業所へ参集します。
(2)対策本部設置訓練(対策本部員向け)
災害が発生した想定で、対策本部を設営します。
(3)机上訓練(イメージ・トレーニング)(対策本部員向け)
災害発生から復旧までの流れを机上で確認します。
(4)安否確認訓練
施設内・外の職員等の安否を実際に確認します。
(5)実働訓練(実地)
機器の操作等、マニュアルに沿って実際に実施します。
(6)総合訓練
地域等と協力し、一連の流れを確認します。
訓練の注意点
始めは、簡単なケースでBCPの訓練を実施しましょう。
例えば、実際に対策本部を設置する予定の会議室に災害対策メンバーを集合し、対策本部の設置や役割の確認を行う訓練などが良いでしょう。
また訓練の進め方として、事前に訓練シナリオを決めておき、進行役が訓練シナリオを1ステップずつ説明し、各班が何を行うか考え、発表するような流れで進めると良いでしょう。この時に、回答できない場合や分からないことがあった場合は、記録を残しておき、BCPへの追記など改善に役立てましょう。
まとめ
ここまで、介護事業所におけるBCP(業務継続計画)について詳しく説明してきましたが、いかがでしたか?
BCPを策定する際は、介護サービス類型ごとの特性を理解したうえで、利用者・入所者や職員の安全を確保しながら、いかにサービスを継続するかという観点が重要となります。
BCPの策定は義務化への対応だけでなく、有事の際のマニュアルとしても重宝します。
また、介護記録や契約書等の重要書類を電子化しておくと、災害時に紛失するリスクを回避できます。
業務効率化だけでなく災害対策も両立したいとお考えの方は、クラウド型の介護ソフト『カイポケ』の導入をぜひご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト