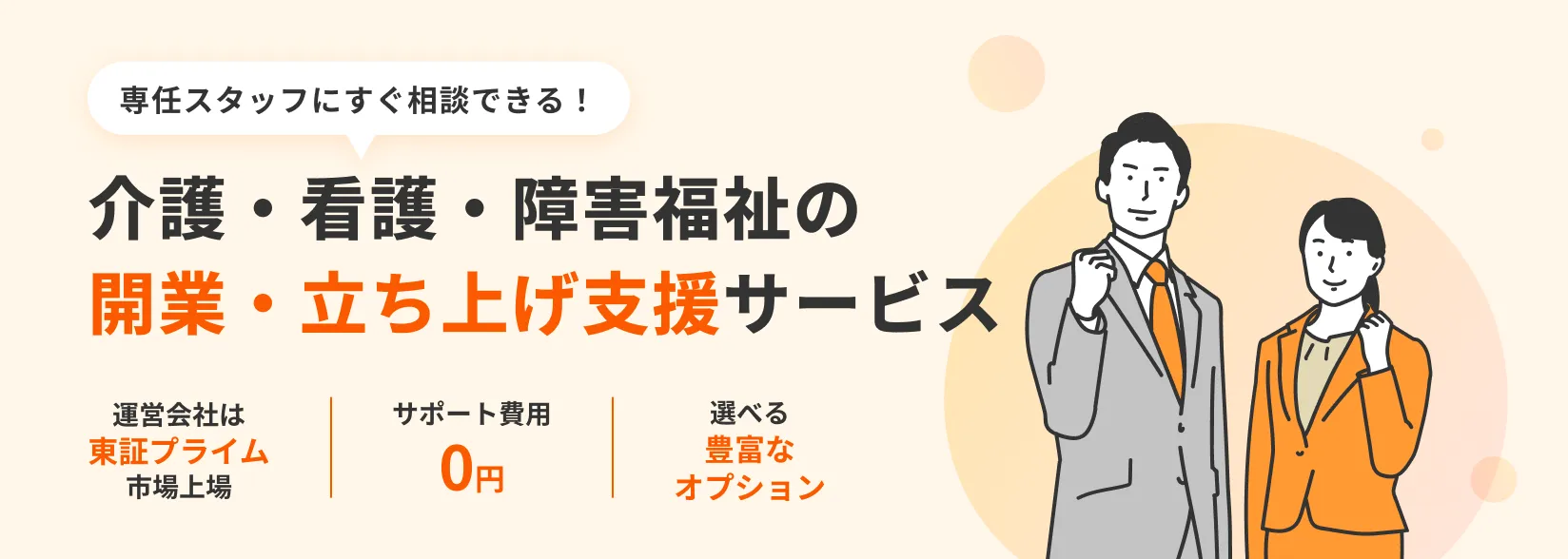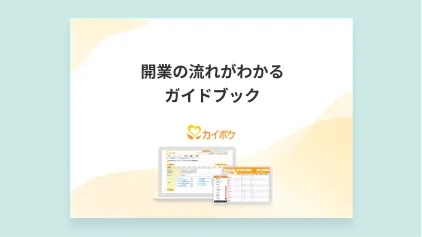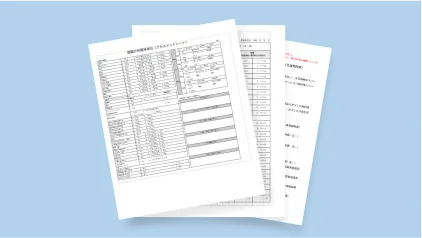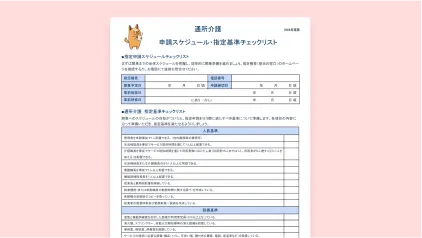介護事業で独立して起業するには?開業の流れ、必要な資格や資金などを解説
介護事業の起業をご検討される方の中には、「介護事業を起業するには何から始めればいい?」「開業するまでの流れは?」「介護事業を起業するために資格は必要?」など疑問に思われてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、介護事業を開業するまでの流れや、立ち上げに必要な資格や資金、独立して介護事業を起業するメリット・デメリットなどを解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
目次
- 介護事業で起業・開業するまでの流れ
- 介護事業立ち上げるために必要な資格・条件は?
- 介護事業を起業するために必要な資金
- 介護事業の開業資金を調達する方法は?
- 独立して介護事業を起業・開業するメリット・デメリット
- 介護事業の開業で困ったら『カイポケ開業支援』に相談
- まとめ
介護事業で起業・開業するまでの流れ
介護事業を起業・開業するまでの流れは、以下のようになっています。
- 経営する介護サービス種別の決定
- 法人設立
- 資金調達
- 設備基準を満たすための物件等の調達
- 人員基準を満たすための人材採用
- 指定申請
1 経営する介護サービス種別の決定
まずは経営する介護サービス種別を決めることになります。
介護サービスは、要介護高齢者の方々の様々なニーズに対応するために、多様な事業種類が設けられています。
事業の概要と開業・運営するための条件、費用等を把握して、経営する介護サービス種別を決めましょう。
介護事業の種類(介護サービス種別)と事業の概要
| 介護事業の種類(介護サービス種別) | 事業の概要 |
|---|---|
| 訪問介護 | 利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
| 訪問入浴介護 | 利用者の自宅を訪問し、介護サービス(浴槽を持参する入浴サービス)を提供する事業 |
| 訪問看護 | 利用者の自宅を訪問し、看護サービスを提供する事業 |
| 訪問リハビリテーション | 利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを提供する事業 |
| 居宅療養管理指導 | 利用者の自宅を訪問し、医療サービスを提供する事業 |
| 通所介護 | デイサービスに通う利用者に介護サービスを提供する事業(利用定員19人以上) |
| 通所リハビリテーション | デイケアに通う利用者にリハビリテーションを含めた介護サービスを提供する事業 |
| 短期入所生活介護 | 特養等の施設に短期間宿泊する利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 短期入所療養介護 | 老健・医療院等の施設に短期間宿泊する利用者に医療・介護サービスを提供する事業 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやサ高住に居住する利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 福祉用具貸与・販売 | 在宅で生活する利用者に福祉用具を貸与・販売する事業 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間365日対応の定期的な巡回や随時対応として利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯に定期的な巡回や随時対応として利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスに通う利用者に介護サービスを提供する事業(利用定員18人以下) |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービスに通う認知症の利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 在宅で生活する利用者に、訪問・通い・宿泊を組み合わせた介護サービスを提供する事業 |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームに居住する認知症の利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやサ高住に居住する利用者に介護サービスを提供する事業(定員数30人未満) |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 特養に入所する利用者に介護サービスを提供する事業(定員数30人未満) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 在宅で生活する利用者に、訪問介護・訪問看護・通い・宿泊を組み合わせた介護サービスを提供する事業 |
| 居宅介護支援 | 在宅で生活する利用者にケアプランの作成、介護事業所との連絡・調整を行う事業 |
| 介護老人福祉施設 | 特養に入所する利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 介護老人保健施設 | 老健に入所する利用者に医療・リハビリテーション・介護サービスを提供する事業 |
| 介護医療院 | 医療院に入所する利用者に医療・介護サービスを提供する事業 |
2 法人設立
介護事業を行うためには、「法人であること」が必要になります。
また、介護サービス種別によって運営できる法人が制限されているので、「株式会社」「社会福祉法人」「医療法人」などの種類から適切な法人を設立しましょう。
3 資金調達
介護事業を開業し、運営するためには、開業資金が必要になります。
物件取得費用や人件費、開業後の運転資金などを自己資金や金融機関からの借入等で準備することになります。
事業の種類や規模によって必要となる設備・人員・準備期間が変わるので、事業計画書を作成し、開業資金としていくら資金調達しなくてはいけないのかを明確にしましょう。
4 設備基準を満たすための物件等の調達
介護事業を開業するためには、『設備基準』を満たしている必要があります。
『設備基準』では介護サービス種別ごとに、事業を行うために準備しなくてはいけない設備・備品等が定められています。
5 人員基準を満たすための人材採用
介護事業を開業するためには、『人員基準』を満たしている必要があります。
『人員基準』では介護サービス種別ごとに、事業を行うために配置しなくてはいけない職種・人数等が定められています。
6 指定申請
介護事業を開業するためには、都道府県や市町村から事業者としての指定(許認可)を受けなくてはいけません。
この指定を受けるための手続きを『指定申請』といいます。
指定申請では、人員基準、設備基準、運営基準を満たしていることを証明する書類等を作成し、審査を受けます。
介護事業立ち上げるために必要な資格・条件は?
経営者・管理者として必要な資格
介護事業を開業する際には、提供する介護サービス種別によって、経営者や管理者に特定の資格や経験が求められる場合があります。
一方で、資格がなくても開業・運営が可能な介護サービス種別も存在します。
ここでは、主要な介護サービス種別に、どのような資格や条件が必要なのか、または資格が不要なのかをみていきましょう。
| 介護サービス種別 | 資格・条件 |
|---|---|
| 訪問介護 | 資格要件なし |
| 通所介護 | 資格要件なし |
| 訪問看護 | (管理者)実務経験のある保健師・看護師 |
| 居宅介護支援 | (管理者)主任介護支援専門員 |
| 福祉用具貸与 | 資格要件なし |
| 介護老人福祉施設 | 社会福祉主事等 |
| 介護老人保健施設 | 医師 |
| 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム) | 資格要件なし |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | (経営者)認知症対応型サービス事業開設者研修
(管理者)認知症対応型サービス事業管理者研修 |
| 小規模多機能型居宅介護 | (経営者)認知症対応型サービス事業開設者研修
(管理者)認知症対応型サービス事業管理者研修 |
介護事業の開業前に満たすべき条件
介護事業を開業するためには、介護サービスの種別ごとに下記3つの基準を満たしていることが条件になります。
- 配置する職種・人数等を定めた『人員基準』
- 設備・備品等を定めた『設備基準』
- 運営する上で遵守すべきルールを定めた『運営基準』
介護事業を起業するために必要な資金
介護事業を開業するために必要な資金は、介護サービス種別によって違いがあるため一概には言えませんが、訪問介護や通所介護などの小規模な介護事業所を開業するためには、一般的に約250万円〜2,000万円ほどが必要と言われています。
また、介護事業の開業資金は、法人の設立費用や物件の契約料、リフォーム費用といった開業前に必要な資金と、人件費や家賃といった開業後の運転資金の2つに分けられます。
開業前に必要な資金の内訳
開業する介護サービス種別によって異なりますが、開業前に必要な資金の内訳は次の通りです。
- 法人の設立費用
- 指定申請にかかる費用
- 物件の初期費用
- リフォーム費用
- 家賃(先払い分)
- 車両の購入・リース費用
- 備品費
- インターネット回線・通信回線の設置費用
- チラシ・ホームページの制作費用
- 人件費(開業準備期間)
開業後に必要な資金の内訳
開業後に必要な資金の内訳は次の通りです。
- 人件費
- 家賃
- 水道光熱費、インターネット回線・通信費用
- 交通費・車両リース費
- 消耗品費
介護事業の開業資金を調達する方法は?
介護事業を開業する際の資金調達方法は、自己資金、金融機関からの借入、家族・知人等からの借入、助成金・補助金などといった方法が考えられます。
自己資金
開業資金が高額になる場合、開業資金のすべてを自己資金でまかなうのは難しいでしょう。
そのため、一定の自己資金を準備し、不足する分について融資を受けるケースが多いようです。
また、融資を受ける場合は、一定の金額(割合)の自己資金が必要とされ、自己資金がゼロの状態では融資を受けられないこともありますので、目標とする融資額に対しておおよそどれくらい自己資金が必要なのかを金融機関のホームページ等で確認しておきましょう。
金融機関からの借入
金融機関は、民間の金融機関と政府系金融機関の2つの選択肢があります。
介護事業の開業のために初めて借入を行う場合は、政府系金融機関である日本政策金融公庫から融資を受けることが多いようです。
助成金・補助金
助成金や補助金は、行政等から支給される返済の必要がない資金です。
助成金・補助金は、開業時に申請できるものと、開業後一定期間が経っていないと申請できないものの二つに大きく分けられます。
開業資金として利用できる創業支援補助金等は地方自治体が行っているものも多いため、ご自身が開業予定の地域で開業時に申請できる助成金・補助金がないか調べてみるのが良いでしょう。
家族・知人等からの借入
親や配偶者、友人等から借入を行う方法もあります。
この場合、返済条件について取り決めをしないと後々トラブルになることがあるので、返済条件などについて契約書を交わしましょう。
独立して介護事業を起業・開業するメリット・デメリット
メリット
独立して介護事業を起業・開業するメリットは次の通りです。
- 事業所の方針などを決めることができる。
- 年収が上がる。頑張った分だけ報酬(給与)を増やすことができる。
- 自分が希望する限り働くことができる。定年がなくなる。
デメリット
独立して介護事業を起業・開業するデメリットは次の通りです。
- 事業についての決定に対する責任とリスクを負うことになる。
- 開業するために資金を準備しなくてはいけない。
- 今まで経験したことがない業務も行わなくてはいけなくなる。
介護事業の開業で困ったら『カイポケ開業支援』に相談
開業の準備を進めていると、「手続きの方法が分からない」「資料作成に時間がかかり、他の準備が進まない」など困る場面もあるかと思います。
そのようなときは、『カイポケ開業支援』にご相談ください。
「介護事業を開業したいが何から始めたらよいか分からない」という方でも、電話やチャットで気軽に相談でき、スケジュールの立て方や各種申請の流れなどをご案内します。
さらに、事業計画の作成支援、融資相談、人材採用、指定申請書類の作成など、幅広いオプションサービスも用意しています。
これらは必要なサービスだけを自由に選択して利用できるため、コストを抑えながら効果的なサポートを受けることが可能です。
まとめ
ここまで、介護事業を開業するまでの流れや、立ち上げに必要な資格や資金、独立して介護事業を起業するメリット・デメリットなどを解説してきました。
介護事業を起業するためには、法人設立や人材採用、指定申請に関わる書類作成などやるべきことが多くあります。
起業の準備をする中で「準備が思うように進まない」「そもそも何から始めたらいいかわからない」などお困りのことがあれば、ぜひ『カイポケ開業支援』にご相談ください。専任スタッフが開業まで支援します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
開業のお悩みを解決するための資料を無料ダウンロード