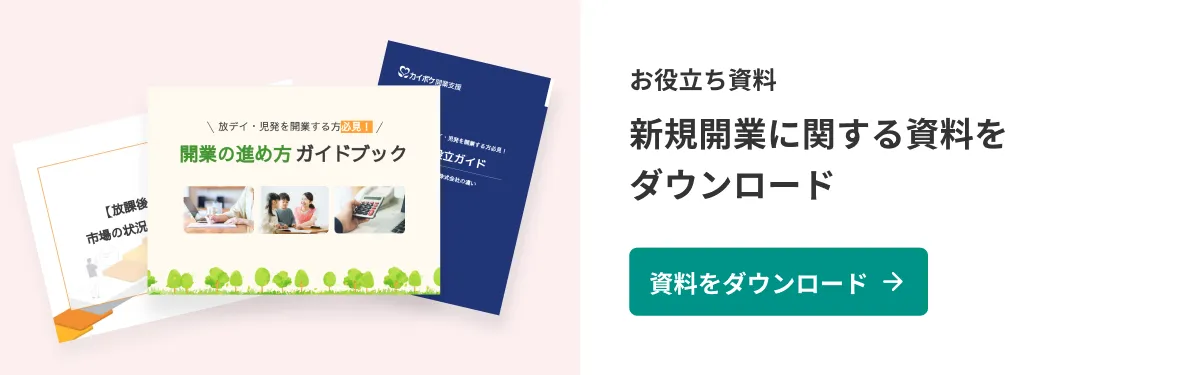社会福祉士が独立するには?独立のメリットや方法を解説!
SMS CO.,LTD
社会福祉士の資格の取得をお考えの方や、すでに資格をお持ちの方の中には、独立を考えているという方もいらっしゃるかと思います。
この記事では、社会福祉士が独立するための具体的な方法やメリット・デメリット、独立を目指せる福祉サービスなどをご紹介します。
目次
- 社会福祉士とは?
- 社会福祉士として独立することは可能?
- 社会福祉士として独立するには
- 社会福祉士が独立する際のメリット・デメリット
- 社会福祉士が独立・開業を目指せる福祉サービス
- 社会福祉士が独立するための具体的な方法
- 開業についてわからないことがあれば『カイポケ開業支援サービス』にご相談ください!
- まとめ
社会福祉士とは?
社会福祉士は社会福祉士及び介護福祉士法に規定された名称独占の国家資格で、主に福祉を必要とする方に対して専門的な知識を生かして支援を行う職業です。
具体的には身体障害、精神障害などの障害がある方や介護を必要とする方、そのご家族から福祉に関する相談を受け、アドバイスするといった業務のほか、必要とする方への福祉サービス事業所、医師や保健医療サービスの紹介などがあります。
また、社会福祉士は働く場所によってどういった役割で仕事をするかが異なります。
例えば高齢者福祉施設・事業所や障害者福祉施設・事業所で働く場合は「生活相談員」、児童相談所や児童福祉施設・事業所で働く場合は「児童福祉司」、学校で働く場合は「スクールソーシャルワーカー」などとして勤務しています。
社会福祉士として独立することは可能?
社会福祉士として独立することは可能です。
独立を目指す場合、福祉施設・事業所や学校などで社会福祉士として一定の期間の経験を積んでからというのが一般的です。
これらは必ずしも必須ではなく、資格取得後にすぐ独立することも可能ですが、多くの社会福祉士の中から選ばれ、依頼を受け付けることを考慮すると実業務の経験や実績はある程度必要です。
社会福祉士として独立するには
社会福祉士として独立するには、以下の2つの方法があります。
- フリーランスになる
- 開業する
フリーランスになる
社会福祉士として独立するためにまず挙げられる方法としては、フリーランスがあります。フリーランスでの独立は、一般的に起業よりも初期費用が抑えられ、手続が少ないことなどが特徴です。 一口にフリーランスといっても、方法は個人事業主型と請負型の2種類があります。 それぞれ詳しく見ていきましょう。
個人事業主型
個人事業主型では、社会福祉士の資格や専門知識を生かして介護・福祉などの講演やアドバイスを行います。また、全国の都道府県社会福祉士会の「ぱあとなあ」に登録することで、成年後見人として業務を受託することも可能です。
成年後見人とは、認知症や障害などの理由で正しい判断が難しい方が、財産上の不利益を被らないように援助を行う人のことです。
請負型
請負型は医療・福祉施設などと契約を結び、社会福祉士の仕事を個人として引き受ける働き方です。 どこにも所属せず、業務委託という形で仕事を請け負いますが、施設等に所属する場合と業務内容は大きく変わらないことが多いです。
開業する
介護、福祉サービスを行う法人の設立を行い、開業することでも社会福祉士として独立が可能です。 事業所の起業には社会福祉士の資格は必須というわけではありませんが、経験を生かすことができる上、有資格者としての信頼もあるので集客に有利という一面があります。
今までの経験から医療や介護、福祉の現場で感じた課題を解決したいという方は開業がおすすめです。 開業はフリーランスと比べると初期費用が多くかかり、法人設立のために必要な手続きも多いものの、福祉の理想を叶えたい方やより多くの方の役に立ちたいといった思いがある方に向いています。
社会福祉士が独立する際のメリット・デメリット
ここでは、社会福祉士が独立する際のメリット・デメリットを、フリーランス・開業のそれぞれの場合で解説します。
フリーランスとして独立した場合
メリット
フリーランスの社会福祉士として働く場合のメリットは、下記の2つが挙げられます。
- 収入が増える可能性がある
- 時間の自由がききやすい
フリーランスの場合は社会福祉士としての業務だけでなく、講演や授業など別の収入源を得ることもできるので、収入が高くなりやすいです。
さらに個人事業主として開業すれば確定申告時に節税効果の高い青色申告ができるので、税金面でのメリットもあります。 また、フリーランスの場合は福祉施設などに所属する場合と比べて働く時間を自分で選べるので、時間を自由に使うことができます。
デメリット
フリーランスの社会福祉士として働くことのデメリットは、主に下記の2つです。
- 収入が不安定になりやすい
- 社会的信用を得にくい
福祉施設などに所属せずに仕事を得る場合は、定期的な収入が確保しにくいため、収入が不安定になりやすいです。 また、フリーランスの場合は有給休暇といった制度もないため、基本的に働かない期間は無収入になります。
さらに、収入が不安定と見なされやすいため、社会的信用を得にくく、ローンが組めない、クレジットカードが作れないといったことが起こることもあります。
事業所を開業する場合
メリット
開業する場合には、下記のようなメリットが挙げられます。
- 収入を増やせる可能性がある
- 理想の福祉サービスを提供できる
福祉系の事業所を設立するなど開業をする場合、やり方によっては収入を増やせる可能性があります。 例えば放課後等デイサービスの場合、想定年収は350~500万円と言われています。
放課後等デイサービスの経営者の年収について知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください。
また、理想としている福祉サービスや、解決したい福祉の課題も開業によって叶えたり解決したりすることができます。 明確にやりたいことがある方にとっては開業という道が適していることも多いです。
デメリット
一方、開業のデメリットは主に下記の2点です。
- 開業する際、法人登記などの手続きや準備が大変
- 初期投資が必要
事業所を開業する場合は、法人の設立から指定申請の準備、物件等の契約など様々なステップがあり、書類等も多いため手続きや準備が煩雑になりやすく、未経験だとかなり大変です。 また、事業所を立ち上げる場合には不動産を借りたり、スタッフの採用をしたり、送迎用の車を買ったりするのにまとまったお金が必要になります。 例えば児童発達支援の開業資金は一般的に1,000万円~1,500万円必要と言われています。
開業資金の内訳や調達方法についてはこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
社会福祉士が独立・開業を目指せる福祉サービス
社会福祉士が開業を目指せる福祉サービスとしては、主に下記の3種類が挙げられます。
- 高齢者福祉サービス
- 児童福祉サービス
- 障害者福祉サービス
それぞれ詳しく見ていきましょう。
高齢者福祉サービス
高齢者福祉サービスでは下記のようなサービスがあります。
| 介護事業の種類(介護サービス種別) | 事業の概要 |
|---|---|
| 訪問介護 | 利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
| 訪問入浴介護 | 利用者の自宅を訪問し、介護サービス(入浴)を提供する事業 |
| 訪問看護 | 利用者の自宅を訪問し、看護サービスを提供する事業 |
| 訪問リハビリテーション | 利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを提供する事業 |
| 居宅療養管理指導 | 利用者の自宅を訪問し、医療サービスを提供する事業 |
| 通所介護 | デイサービスに通う利用者に介護サービスを提供する事業(利用定員19人以上) |
| 通所リハビリテーション | デイケアに通う利用者にリハビリテーションを含めた介護サービスを提供する事業 |
| 短期入所生活介護 | 特養等の施設に短期間宿泊する利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 短期入所療養介護 | 医療機関や老健・医療院等の施設に短期間宿泊する利用者に医療・介護サービスを提供する事業 |
| 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやサ高住に居住する利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 福祉用具貸与・販売 | 在宅で生活する利用者に福祉用具を貸与・販売する事業 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間365日対応できる体制あり、定期的な巡回や随時通報経の対応として利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯に定期的な巡回や随時通報経の対応として利用者の自宅を訪問し、介護サービスを提供する事業 |
| 地域密着型通所介護 | デイサービスに通う利用者に介護サービスを提供する事業(利用定員18人以下) |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービスに通う認知症の利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 在宅で生活する利用者に、訪問・通い・宿泊を組み合わせた介護サービスを提供する事業 |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームに居住する認知症の利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームやサ高住に居住する利用者に介護サービスを提供する事業(定員数30人未満) |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 特養に入所する利用者に介護サービスを提供する事業(定員数30人未満) |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 在宅で生活する利用者に、訪問介護・訪問看護・通い・宿泊を組み合わせた介護サービスを提供する事業 |
| 居宅介護支援 | 在宅で生活する利用者にケアプランの作成、介護事業所との連絡・調整を行う事業 |
| 介護老人福祉施設 | 特養に入所する利用者に介護サービスを提供する事業 |
| 介護老人保健施設 | 老健に入所する利用者に医療・リハビリテーション・介護サービスを提供する事業 |
| 介護医療院 | 医療院に入所する利用者に医療・介護サービスを提供する事業 |
高齢者福祉サービスの起業についての詳細は、こちらの記事をご確認ください。
児童福祉サービス
児童福祉サービスのうち、障害児を対象としたものには次のようなサービスがあります。
| 児童福祉サービス(障害児が対象) | サービス概要 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学の障害児に対する通所の発達支援を行う療育の場、もしくは障害児や家族への支援や障害児を預かる施設に対する支援 |
| 医療型児童発達支援 | 上記のうち、医療の提供を行うもの |
| 放課後等デイサービス | 放課後または休暇中の就学している障害児に対し、生活能力向上のための訓練を継続的に提供する支援 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を利用中または利用予定の障害児を訪問し、保育所等の安定した利用を促進する支援 |
| 福祉型障害児入所施設 | 従来の障害種別の施設と同等の支援、障害に応じた適切な支援 ※18歳以上の入所者には自立を目指した支援を提供 |
| 医療型障害児入所施設 | 上記のうち、医療の提供を行うもの |
参照元:全国社会福祉協議「「障害福祉サービスの利用について」
障害者福祉サービス
障害福祉サービスでは下記のようなサービスがあります。
| 障害福祉サービス | サービス概要 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅での入浴、排せつ、食事の介護等 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有し、常に介護が必要な人に対する、自宅での入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動支援、入院時の支援等総合的な支援 |
| 同行援護 | 視覚障害により外出が著しく困難な人に対する、移動にあたっての援護や必要な情報の提供 |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人に対する、行動時の危険回避のために必要な支援、外出支援 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に対する、居宅介護等複数の包括的なサービス |
| 短期入所 | 自宅で介護する人が病気などの場合に施設で行う、短期間(夜間含む)の入浴、排せつ、食事の介護等 |
| 療養介護 | 医療と介護を必要とする人に対して医療機関で行う、機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に対して昼間に行う、入浴、排せつ、食事の介護等や、創作活動または生産活動の機会の提供 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に対して夜間や休日に行う、入浴、排せつ、食事の介護等 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うために行う、定期的な居宅訪問、日常生活における課題把握のための随時の訪問を通した必要な支援の提供 |
| 共同生活援助 | 夜間や休日、共同生活を行う住居での相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活の援助 |
| 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるように行う、一定期間の身体機能の維持、向上に必要な訓練 |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるように行う、一定期間の生活能力の維持、向上に必要な支援、訓練 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に対して行う、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上に必要な訓練 |
| 就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人の雇用による就労機会の提供、能力等の向上に必要な訓練 |
| 就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な人に対する就労の機会の提供、能力等の向上に必要な訓練 |
| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人に対する、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援 |
社会福祉士が独立するための具体的な方法
ここでは、社会福祉士が独立するための方法をフリーランスの場合と起業する場合に分けてより具体的に解説します。
フリーランスの場合
請負型
フリーランスで働く場合、請負型は以下のような流れで独立することが多いです。
- 社会福祉士として一定の経験を積む
- 以前の職場や関わりのあった施設などから個人的に業務を受託する
個人事業主型
個人事業主型は、以下の流れで独立するのが一般的です。
- 社会福祉士として一定の経験を積む
- 社会福祉士で構成される職能団体である公益社団法人 日本社会福祉会の「独立型社会福祉士名簿」への登録を行う
- 支援を必要としている個人や団体、行政などから仕事を受注する
独立型社会福祉士名簿への登録は必須ではないものの、社会的信用を得たり、実務経験を証明したりすることに役立ちます。
独立型社会福祉士名簿に登録するには下記の条件を満たす必要があるので、事前に確認しておきましょう。
引用元:公益社団法人 日本社会福祉士会「独立型社会福祉士名簿とは」
- 1. 都道府県社会福祉士会の会員である者
- 2. 認定社会福祉士認証・認定機構により認定された「認定社会福祉士」である者
- 3. 本会へ事業の届出をした者
- 4. 本会独立型社会福祉士委員会主催の独立型社会福祉士に関する研修を修了した者
- 5. 毎年の事業報告書の提出を確約した者
- 6. 社会福祉士賠償責任保険等への加入を確約した者
- 7. 第15条で定める名簿登録者の義務の遵守を確約した者
- 8. 独立型社会福祉士名簿の公開に同意した者
開業する場合
開業までの流れ
介護、福祉事業の開業には、一般的に様々な手続きが必要です。 ここでは例として放課後等デイサービスにおける開業までの流れをご紹介します。
- 法人設立
- 事業計画書の作成
- 資金調達
- 物件探し
- 職員の採用
- 物件のリフォーム
- 備品等の調達
- 指定申請(行政から許認可を受けるための手続き)
- 開業
児童発達支援や介護事業等でも大きな流れとしては同様です。 開業について、詳細を知りたいという方はこちらをご覧ください。
開業に必要な準備期間
一般的に、福祉サービスの起業には半年から1年ほどの準備期間が必要です。 開業が初めての方はつまずくことも多いので、さらに時間がかかる可能性も十分にあります。 開業する際は、時間に余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
開業についてわからないことがあれば『カイポケ開業支援サービス』にご相談ください!
もし開業をお考えの方で、開業の手順に不安があるという方は、『カイポケ開業支援』の利用がおすすめです。
『カイポケ開業支援』では、開業に必要な様々なサポートを初期費用・サポート費用無料で提供しています。
行政手続きに関する情報提供や開業スケジュールの作成など、開業が初めての方にも安心できるサポートとなっています。
「身近に開業について相談できる人がいない」、「インターネットでの情報収集ではわからないことが多い」といった悩みをお持ちの方は、こちらからカイポケ開業支援へご相談ください。
まとめ
ここまで、社会福祉士の独立について解説してきました。 社会福祉士は、社会的信用が得やすく、独立の仕方によっては集客や採用にも有利に働くことが多い資格です。 資格の取得をお考えの方はこの記事を参考にしていただき、資格取得や独立開業をご検討されてはいかがでしょうか。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※開業について詳しい資料をご覧になりたい方は、下記より無料でダウンロードいただけます。