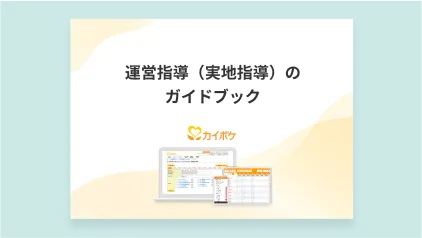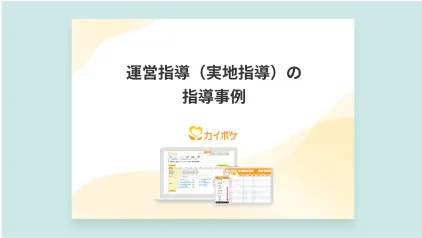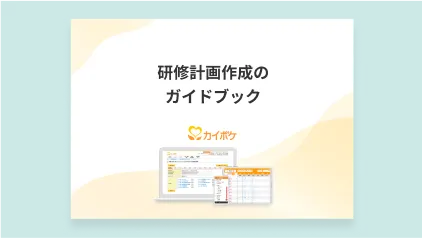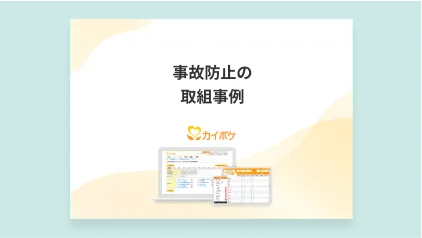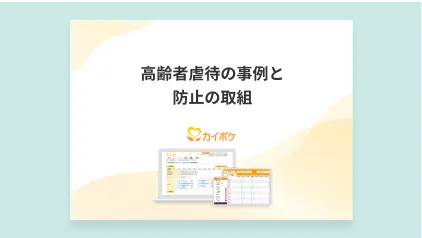介護保険請求の過誤とは?過誤申立の流れと事由コードを解説
介護事業所の請求業務をはじめて担当することになった方は、『過誤ってなんだろう?』、『過誤に該当しないためにはどうすればいいの?』といった疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、介護保険請求における過誤について、概要と再請求までの流れなどを説明しています。
目次
介護保険請求における過誤とは?
介護保険請求における過誤とは、事業所が国保連に対して請求し、支払いを受けた金額について誤りがあることを言います。
誤りがあった場合は、保険者(市町村)へ過誤申立を行い、介護給付費明細書を取り下げる手続きを行い、正しい金額で再請求することになります。
介護保険請求における返戻とは?
介護保険請求における返戻とは、事業所が請求した内容や金額に不備が見つかり、国民健康保険団体連合会(以下、国保連)から事業所へ介護給付費明細書が戻されることを言います。
介護保険請求における保留とは?
介護保険請求における保留とは、介護給付費明細書に対して、居宅介護支援事業所等から給付管理票の提出がなかった場合や提出された給付管理票が返戻となった場合などに、国保連から支払いが行われずに請求データを国保連にて保留することを言います。
過誤申立から再請求の流れ
請求して入金された介護報酬に誤りが見つかった場合、保険者である市町村に過誤申立書等を提出します。
市町村から国保連へ過誤の内容について連絡され、国保連から『介護給付費過誤決定通知書』が届き、介護報酬の支払額が減額調整されます。
そして、正しい金額で再請求することになります。
過誤の種類(同月過誤・通常過誤)
過誤の手続きには、同月過誤と通常過誤の2種類があります。
通常過誤
通常過誤とは、同月に再請求はせず過誤申立を行い、介護給付費明細書の取り下げを行うことを言います。
過誤の決定を受けた介護給付費明細書の金額は、一旦全額返金し(支払われる介護報酬から減額され)、正しい金額で再請求します。
同月過誤
同月過誤とは、過誤申立と再請求の審査を同月に行い、差額の調整を行うことを言います。
通常過誤では、全額返金して再請求することになるので、その手続きの期間中、入金が遅れることになりますが、同月過誤では、誤って入金された金額と正しい請求金額の差額だけを調整することになるので、資金面での負担が少ないということになります。
過誤のリスクを軽減するためには?
過誤があった場合(通常過誤で処理する場合)、一旦全額返金し、正しい金額や情報で再請求した後に再度審査を受けて入金されるまでの資金面での負担があります。
また、請求業務の負担が増えるというデメリットもあります。
このようなリスクを軽減するためには、「請求内容や入金に対するチェック体制を整備する」と「使いやすい介護請求ソフトを導入する」といった方法が挙げられます。
運営指導(実地指導)対策ガイドをご用意しています。
今すぐ無料でダウンロード→
請求内容や入金に対するチェック体制を整備する
介護給付費を計算するためのルールを把握し、チェックを行う体制を構築しましょう。
特にチェックの担当者は、加算の算定要件と減算の適用要件を把握し、提供しているサービスや事業所の体制等の実態が「加算の算定要件を満たしているのか」、「減算の適用要件に該当していないか」を定期的にチェックするようにしましょう。
介護請求ソフトを導入する
過誤のリスクを軽減するためには、介護請求ソフトを導入することをおススメします。
介護給付費明細書を作成するための基となるデータを一元的に管理することで、転記によるミスを減らし、入力とチェックの負担を減らすことができます。
また、介護請求ソフトの機能のひとつとして、請求データの整合性が取れていない場合にアラートが表示される機能がありますので、ミスを減らすことができるでしょう。
介護ソフトの徹底比較ガイドをご用意しています。
今すぐ無料でダウンロード→
まとめ
介護保険請求において過誤は、資金面での負担が発生することがあり、再請求のための業務負担が増えることから避けたい事象です。
過誤のリスクを減らすためには、介護請求ソフトの機能などを活用し、ミスを減らし、定期的に請求・入金のチェックを行う体制を構築する必要があります。
運営指導にて誤った請求が見つかると、不正請求と判断され、行政処分に至る場合もありますので、定期的なチェックは必ず行いましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト