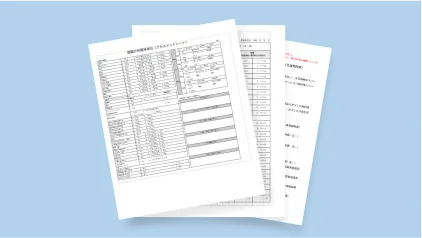伝わる介護記録の書き方とシーン別の記入例【無料テンプレート付き】
日々、利用者様に介護サービスを提供するなかで、必ず作成する「介護記録」。
利用者様へどのようなサービスを提供したのかを記録・保管する大切な書類です。
しかし、作成する際に「何を書けばいいか分からず、時間が掛かる」「これで他の職員に伝わるだろうか」とお悩みではありませんか。
この記事では、読み手に伝わる介護記録の書き方やシーン別の記入例、使ってはいけない表現などを解説していきます。
目次
介護記録とは?
介護記録とは、利用者様に提供したサービスの内容等を記録する書類です。
介護記録は、運営基準に作成・保管・交付等の義務が定められている書類であり、利用者様に、いつ、だれが、どのようなサービスを提供したのかを記載します。
また、介護記録は、ケアプランに定めた目標を達成するために提供したサービスの内容と利用者様の状態を記載するので、モニタリングの際の「適切にサービスを提供できているか」「目標を達成できたか」などを確認するためにも使用します。
(サービスの提供の記録)
第十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」より引用
介護記録に記載すべき内容・項目
介護記録には、指定されたフォーマットはありませんが、以下のような内容・項目を含める必要があります。
- 利用者様の氏名
- サービスを提供した介護職員等の氏名
- 利用者様の健康状態
- サービスを提供した日時
- 提供したサービスの具体的な内容
- 利用者様の反応、希望
介護記録を作成する目的
介護記録を作成する目的は、「介護報酬を請求する根拠書類として使用するため」や「介護の質を向上させるため」、「事故など万が一のことが起きた時に職員を守るため」となっています。
介護報酬を請求する根拠書類として使用するために作成する
介護サービス事業所は、利用者に介護サービスを提供し、その対価として介護報酬を請求します。
介護記録は、請求における根拠書類としての役割があるので、適切に作成し、保管しなければいけません。
また、運営指導において定期的にチェックされ、もし介護記録がないとサービス提供の事実を証明できないため、報酬の返還を求められる可能性もあります。
介護の質を向上させるために作成する
介護記録は、ケアの内容や方針を変更する際にも使用されます。
介護サービスは、ケアプランや介護計画に沿って提供します。
サービスを提供する中で利用者様の状態や意向が変化することもあるので、それを記録しておくことで、ケアプランや介護計画を更新する際に、介護記録の内容を参考にすることができます。
事故など万が一のことが起きた時に職員を守るために作成する
万が一事故が発生してしまった場合にも介護記録を使用し、事実関係等を確認します。
日々のサービス内容や利用者の状態を記録しておくことで、適切にケアを行った根拠を確認することができ、トラブルから従業員を守ることにも繋がります。
伝わる介護記録の書き方のポイント
ここでは、介護記録の内容が読んだ人に伝わるように記載する方法をご紹介します。
「5W1H」で言語化する
介護記録は、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」を具体的に記載しましょう。
5W1Hを明確にすることで、正確な内容を記録することができ、相手にも伝わりやすい形式で文章をまとめることができます。
常体(だ・である調)で書く
先述のとおり、介護記録は運営基準に定められる書類です。
このような書類は一般的に、敬体(です・ます)よりも常体(だ・である)で統一することが望ましいとされています。
客観的な事実を書く
介護記録は起こった事柄や利用者様の状態、行動、発言など、見聞きした情報をありのままに記録することが求められます。
特にケアに対する想いや意見など、自身の主観による内容は避けるようにしましょう。
介護記録を効率的に作成する方法
介護記録を作成する際、記録する箇所を探したり、どのように表現すればいいのか迷ってしまったりすることで時間がかかってしまいます。
ここでは、介護記録の作成を効率化するための方法をご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
介護記録ソフトを導入する
介護記録を効率的に作成するには、介護記録ソフトを導入するのが近道です。
介護記録ソフトは、利用者様ごとに記録を入力する箇所が設けられているので記録業務を効率化することができます。また、これまでに入力した記録から経過をかんたんに確認できるため、適切な介護サービスの提供にもつながります。
テンプレートを使用する
介護記録ソフトを導入できない場合は、Excelなどで介護記録のテンプレートを用意しましょう。
テンプレートを使用することで、どこに何を書くのかがわかりやすく、手書きで介護記録を作成するよりも効率化を図ることができます。
使用する文章・語句を統一する
介護記録で使用する文章、語句を統一し、定型文や予測変換できるようにすると介護記録の作成を効率化することができます。
また、同様の表現を使用することで、事業所内で共通の認識を持つことができます。
インカムと文字起こしソフト・アプリを導入する
インカムと文字起こしソフトを導入することで、介助をしながら話したことを記録として残すことができ、介護記録の作成を効率化することができます。
また、インカムを導入することによってスムーズな情報共有も実現できます。
【介護予防】経過記録のひな型をご用意しています。
今すぐ無料でダウンロード→
シーン別の介護記録の記入例
ここからは、介護現場でよくみられるシーン別に介護記録の例をご紹介します。
食事の場面
スタッフが〇〇様に「昼食ですよ」と声掛けしながら配膳したが、表情が暗く手を付けようとしなかった。スタッフが「食欲がないですか」と声かけしながら介助すると、味噌汁は全量召し上がり、ご飯とハンバーグは「おなか一杯」と話し、5割ほど残した。
入浴
〇〇様のバイタルサイン:血圧130/70mmHg、脈拍60回/分、体温36.0度と正常値を確認。スタッフが「お風呂ですよ」と声かけしながら脱衣介助を行う。〇〇様も自分でシャツを脱いだ。〇〇様が洗顔と腹部など手の届く範囲で洗身を行った。洗髪や腹部以外の洗身はスタッフが行い、その後、入浴の介助をした。
排泄
〇〇様のオムツ交換を行った。昨日から便が出ておらず下剤を服用し排便を促したことで、泥状便を多量に確認した。〇〇様は「すっきりした」とおっしゃられていました。
レクリエーション
〇〇様はレクに参加され、△△様と一緒に折り紙を行い笑顔で楽しんでいた。細かい作業で困っている様子だったので、スタッフが「お手伝いしましょうか」と声かけし、折り返しをサポートした。
服薬
「〇〇さん、食後の薬ですよ」とスタッフが声かけし、オブラートに包んだ薬を手渡した。〇〇様は表情をしかめて、湯呑に入ったとろみのついたポカリに薬を入れると、スプーンですくって一人で服用した。スタッフは服用の様子を確認した。
ヒヤリハット
昼食介助のため〇〇様のベッドをギャッチアップし始めたところ、右腕がベッドから外へはみ出していたため、柵との間に挟まりそうになった。寸前のところでスタッフが気づき、急いでベッドをもとに戻し、腕にけがを負っていないか確認した。
介護記録で使ってはいけない表現と言い換えの例
介護記録で使ってはいけない表現として、利用者様の人格を否定する侮辱的表現や、主観的な表現、難解な専門用語や、命令を想起させる表現などが挙げられます。
特に使用すべきでない表現として、利用者様を侮辱するような表現に注意しましょう。
例として3つの言葉を紹介しますので、言い換えるようにしましょう。
認知がある
「認知がある」と表現すると「認知機能がある」という意味になってしまいます。
現場では認知症の略語のような意味合いで使われる表現ですが、介護記録には不適切です。
また、認知症は利用者様の行動に影響を与えるものですので、「認知症だから」という表現にならないよう気をつけましょう。
言い換え例:「認知症」(略さずに表記する)、「認知症の症状により、同じ内容を何度も話された」(具体的な状況を客観的に記述)
徘徊
「徘徊」のもともとの意味は「あてもなく歩き回る・うろうろする」であり、認知症を有する方の行動とは一致しません。認知症を有する方は「目的はあるが、認知症の影響で忘れてしまう」という意味合いですので、徘徊という表現は控えましょう。
言い換え例:「歩き回る」、「フロアと居室を5分ほど行き来された」(具体的な行動を記述する)
不潔行為
こちらも同様に、利用者様は意図して不潔なことをしているわけではなく、認知症の影響によりそう見えているだけですので、そうした影響を理解した上で、どのような行為をしているのかをありのままに書くようにしましょう。
言い換え例:「おむつを外されており、便がついた手で服やベッド柵を触っていた」(具体的な行動を記述する)
介護記録の社内研修を実施しましょう
介護職員として、適切な介護を提供し、正確な介護記録を作成できるようになることは、資質向上につながるので、介護職員全体を対象とした研修会を定期的に行うとよいでしょう。
介護記録に関する研修の項目の例
- 記録の基本的な書き方
- 観察のポイント
- 簡潔で客観的な表現方法
- 使ってはいけない表現と言い換えの例
- 介護記録を使った情報共有
- ケアの質の向上につながる介護記録の書き方
- リスクマネジメントのための介護記録の書き方
年間・個別研修計画ガイドをご用意しています。
今すぐ無料でダウンロード→
まとめ
ここまで介護記録について詳しく説明してきましたが、いかがでしたか?
介護記録は、サービスを提供する都度、作成しなければいけない書類です。
サービスの質の向上やリスクマネジメントの観点からも、誰が見ても事実を把握できるように作成しなければいけません。
また、介護現場での生産性向上の観点からは介護記録を効率的に作成することが求められています。
「介護記録の作成を効率化したい」と考えている方は、ぜひ介護ソフト『カイポケ』の導入をご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
帳票に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト