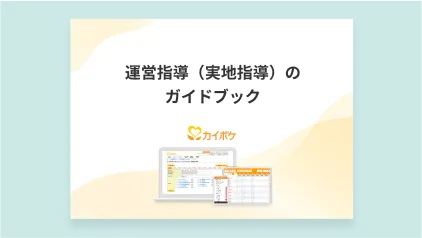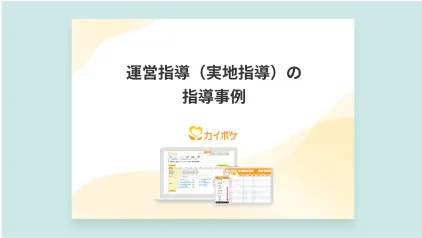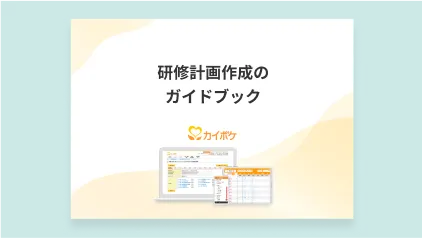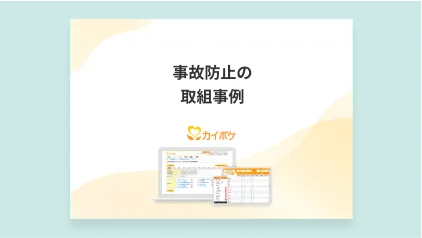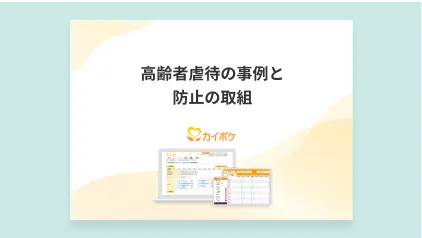ケアマネジャーが感染症を予防するための対策とは?マニュアルも合わせてご紹介
新型コロナウイルスなどの感染症が流行する中で、居宅介護支援事業所を運営する皆様は感染予防や感染拡大の防止に特に気を使っていらっしゃることでしょう。
そのような中で、「現在行っている感染症対策は十分なのかな?」や「感染症対策のマニュアルは何を参考にすればいいの?」といった悩みをお持ちの方もいるかもしれません。
この記事では、管理者・経営者の皆様に向けて、居宅介護支援事業所における感染症の予防や拡大を防止するための方法などについて解説していきます。
目次
ケアマネジャーが対策するべき感染症の種類とは?
感染症とは、病気の原因となるようなウイルスや細菌などが体の中に入り、熱が出たり下痢になったり、具合が悪くなることを指します。
感染症には様々な種類がありますが、具体的に居宅介護支援事業所で対策すべき感染症の病原体について例をご紹介します。
感染症の例
- 新型コロナウイルス
- インフルエンザウイルス
- ノロウイルス
- 結核菌
- 腸管出血性大腸菌 (O157など)
- レジオネラ属の細菌
- ヒゼンダニ(疥癬)
- B型肝炎ウイルス(ウイルス性肝炎)
- MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)
- MDRP(多剤耐性緑膿菌)
- 水痘・帯状疱疹ウイルス(帯状疱疹)
- アタマジラミ
クロストリジウム・ディフィシル菌(偽膜性大腸炎)
など
ケアマネジャーの感染症拡大を予防するための対策とは?
ケアマネジャーが感染症拡大を予防するためには、どのような対策が必要になってくるのでしょうか。
居宅介護支援の運営基準には、『感染症の予防及びまん延の防止のための措置』という項目があり、
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
- 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
- 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
といったことが定められています。
それでは、居宅介護支援事業所で感染症のまん延を防止するためには、どのような対応が推奨されているのかを見ていきましょう。
長崎市介護支援専門員連絡協議会のマニュアル
長崎市介護支援専門員連絡協議会は、「新型コロナウィルス感染症に係る居宅介護支援事業所における業務の考え方(居宅介護支援事業所版BCP)」を発表しており、日頃から徹底した予防策を講じる大切さを説いています。
それでは、居宅介護支援事業所における「感染の予防」と「感染拡大の防止」のための対策を、冊子に沿って見ていきます。
感染予防のための対策
【防護品などの衛生材料を確保】
- 事業所で感染予防に必要な物品のリストを作成する。
- マスクや消毒薬などが品薄の状況であることを考慮して、在庫管理を徹底する。
- 緊急時の訪問も想定して備品の確保を図る。
【事務所内の掃除・消毒】
- 通常の掃除に加えて、共有で使用する電気のスイッチや電話機、来所者が使用する玄関扉や相談テーブルなどの掃除も定期的に行う。
- 事務所内の換気は時間を決め行うなどして、風通しの悪い空間を作らない。
- 職員が新型コロナウィルスに感染した疑いが発生した際は、十分な換気を行い、マスク手袋を着用して、その職員が使用(接触)した場所を消毒用アルコールでふき取る。
感染拡大を防止するための対策
【事業所に出入りする際の注意点】
- 事務所出入口に、手指消毒を行うための消毒薬を設置する。
- 業者の出入りは可能な限り玄関で対応をし、事業所内に長期滞在する際は、検温など健康状態の確認も検討する。
【訪問時の注意点】
- 自分自身の健康管理に留意し、体調の変化があった際は訪問を見合わせる。
- 訪問前に、利用者等の体調を確認し、発熱等がないかを事前に把握する。
- 訪問時は、換気を徹底すると同時に、可能な限り短い時間でできるよう工夫をする。
- 訪問前後の手洗いやうがい、訪問時の咳エチケットは徹底する。
- 市内の感染状況によっては、連続しての訪問は控える。
【職員のメンタルケアに対する体制を構築】
感染症が流行する中でサービスを提供することで、職員のストレスが高まるため、以下のような事前の対策をします。
- 職員のメンタルケアをサポートできる仕組みを構築する。
- カウンセリングなどの導入を検討する。
- 規則正しい生活を送る、身近な人たちとつながりを保って孤立を避けるなど、職員にセルフケアを促す。
厚生労働省のマニュアル
厚生労働省は「介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き」というマニュアルを発表しています。この中には、感染を予防するために管理者や職員が日頃から取り組むべきことについての記載がありますので、詳しくご紹介していきます。
感染予防のための管理者の役割
感染防止のために、管理者は日頃から以下のような取組みを行うことが重要です。
- 地域の感染症の発生状況を把握。
- 連絡先の一覧を作成するなど、日頃から医師や保健所等との連携体制を構築。
- 感染症を疑う利用者がいる場合は、速やかに受診を勧奨。
- 近隣事業所との情報交換を密に行い、地域レベルで効果的な対応ができるようにする。
- 職員の健康管理にも留意し、感染症が疑われる場合は、速やかに医療機関の受信を進めるなど助言を行う
感染予防のための職員の役割
感染症の予防のために、以下の対応を職員全員で取り組むことが重要です。
- 感染対策の基本的な考え方、個人用感染防護具の装着方法等を習得する。
- 事業所内での感染対策の研修や、企画・運営等にも積極的に参加する。
- 感染症発生時の対応がまとめてある書類の場所を把握する。
- 職員同士で声をかけあい、感染対策を徹底する。
- 利用者が発熱している等、体調に心配がある場合には、かかりつけ医と連携し、適切な対応につなげられるようにする。
ケアマネジャーの新型コロナウイルス感染症に対する臨時的な対応とは?
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厚生労働省は事務連絡で、ケアマネジメント業務の弾力的な対応などの臨時的な対応策を示してきました。
ここからは、厚生労働省が示した臨時的な対応の中身について、詳しく見ていきましょう。
ケアマネジメント業務の弾力的な対応
ケアマネジメント業務の弾力的な対応について、事務連絡を抜粋してご紹介します。
【利用者宅の訪問】
- 感染拡大防止の観点を踏まえて、「利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能」。
【サービス担当者会議】
- 「感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能」。
- 利用者様の状態に大きな変化が見られないなど、居宅サービス計画の変更内容が軽微な場合は、「サービス担当者会議の開催は不要」。
【モニタリング時の居宅訪問】
- モニタリングについては、利用者様の事情によって利用者様の自宅を訪問できないなどやむを得ない理由がある場合は、「月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能」。
【サービス変更時のケアプラン見直し作成】
- ケアプランの変更については、「サービス提供後に行っても差し支えない」。
介護報酬の弾力的な対応
介護報酬の柔軟な取扱いについて、事務連絡を抜粋してご紹介します。
【減算にならない特例】
- やむを得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合においては、「40件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能」。居宅介護支援費Ⅱの場合は45件以上。
- 感染拡大防止の観点を踏まえて、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、「居宅介護支援費の減額を行わないことが可能」。
- 特定事業所集中減算について、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、「減算を適用しない取扱いが可能」。
【退院・退所加算の特例】
- 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、「病院等の職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定することが可能」。
【特定事業所加算の特例】
- 特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告については、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合、「電話、文書、メール、テレビ会議等を活用するなどにより、柔軟に対応すること」ができる。
【サービス利用実績がない場合の居宅介護支援費の特例】
- モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、「新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能」。
まとめ
ここまで、ケアマネジャーが居宅介護支援事業所で対策するべき感染症の種類や、感染症を予防する方法について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
居宅介護支援事業所で感染症を予防するにあたり、厚生労働省や静岡県介護支援専門員協会、長崎市介護支援専門員連絡協議会などが参考にするべきマニュアル等を公開しています。これらを参考にしながら、ご自身の事業所における感染症対策のマニュアル・指針を整備していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト