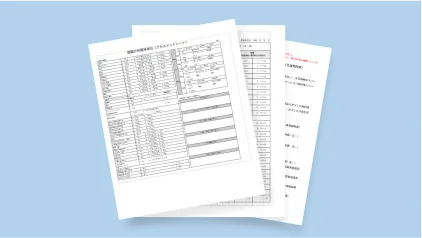アセスメントシートの書き方と様式の無料ダウンロード
居宅介護支援事業所等のケアマネジャーが実施するケアマネジメントは、利用者の状況等を把握する「最初の面接・相談(インテーク)」、利用者の解決すべき課題(ニーズ)を明確にする「アセスメント」、課題分析で明確になった課題(ニーズ)を解決するための「ケアプラン原案の作成」、ケアプランを実施するための「サービスの調整」、ケアプランの目標・サービス内容の共有・ケアプランの確定のための「サービス担当者会議の開催」、サービス利用開始後の経過の把握・評価を行う「モニタリング」、モニタリングの結果から必要に応じた「再アセスメント、ケアプランの見直し」といった流れで行われています。
このような流れの中で、利用者の解決すべき課題(ニーズ)を明確にするために実施されるアセスメントでは、インテークで把握した情報に加え、利用者の様々な情報を集める必要があります。
このアセスメントの際に使用する書類が『アセスメントシート』となります。
この記事では、アセスメントシートの項目や書き方、注意点などについて説明していますので、ぜひ最後までお読みください。また、全国社会福祉協議会の「居宅サービス計画ガイドライン」に沿ったアセスメントシートの様式も無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
目次
1.アセスメントシートとは?
アセスメントシートとは、ケアマネジャーが利用者の解決すべき課題(ニーズ)を明確にするために行うアセスメントで使用する書式です。
課題の分析は、厚生労働省(厚生省)から通知されている「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」にて、課題分析標準項目として、基本情報に関する9項目と課題分析(アセスメント)に関する14項目の合計23個の項目について情報を集め、課題を分析することが示されています。
課題分析標準項目の23項目
基本情報に関する項目
| No. | 標準項目名 | 項目の主な内容(例) |
|---|---|---|
| 1 | 基本情報(受付、利用者等基本情報) | 居宅サービス計画作成についての利用者受付情報(受付日時、受付対応者、受付方法等)、利用者の基本情報(氏名、性別、生年月日・住所・電話番号等の連絡先)、利用者以外の家族等の基本情報、居宅サービス計画作成の状況(初回・初回以外)について記載する項目 |
| 2 | これまでの生活と現在の状況 | 利用者の現在の生活状況、これまでの生活歴等について記載する項目 |
| 3 | 利用者の社会保障制度の利用情報 | 利用者の被保険者情報(介護保険、医療保険等)、年金の受給状況(年金種別等)、生活保護受給の有無、障害者手帳の有無、その他の社会保障制度等の利用状況について記載する項目 |
| 4 | 現在利用している支援や社会資源の状況 | 利用者が現在利用している社会資源(介護保険サービス・医療保険サービス・障害福祉サービス、自治体が提供する公的サービス、フォーマルサービス以外の生活支援サービスを含む)の状況について記載する項目 |
| 5 | 日常生活自立度(障害) | 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 |
| 6 | 日常生活自立度(認知症) | 「認知症高齢者の日常生活自立度」について、現在の要介護認定を受けた際の判定(判定結果、判定を確認した書類(認定調査票、主治医意見書)、認定年月日)、介護支援専門員からみた現在の自立度について記載する項目 |
| 7 | 主訴・意向 | 利用者の主訴や意向について記載する項目 家族等の主訴や意向について記載する項目 |
| 8 | 認定情報 | 利用者の認定結果(要介護状態区分、審査会の意見、区分支給限度額等)について記載する項目 |
| 9 | 今回のアセスメントの理由 | 今回のアセスメントの実施に至った理由(初回、要介護認定の更新、区分変更、サービスの変更、退院・退所、入所、転居、そのほか生活状況の変化、居宅介護支援事業所の変更等)について記載する項目 |
課題分析(アセスメント)に関する項目
| No. | 標準項目名 | 項目の主な内容(例) |
|---|---|---|
| 10 | 健康状態 | 利用者の健康状態及び心身の状況(身長、体重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、褥そうの有無等)、受診に関する状況(かかりつけ医・かかりつけ歯科医の有無、その他の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等)、服薬に関する状況(かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施状況等)、自身の健康に対する理解や意識の状況について記載する項目 |
| 11 | ADL | ADL(寝返り、起きあがり、座位保持、立位保持、立ち上がり、移乗、移動方法(杖や車椅子の利用有無等を含む)、歩行、階段昇降、食事、整容、更衣、入浴、トイレ動作等)に関する項目 |
| 12 | IADL | IADL(調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の運転等)に関する項目 |
| 13 | 認知機能や判断能力 | 日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている場合の中核症状及び行動・心理症状の状況(症状が見られる頻度や状況、背景になりうる要因等)に関する項目 |
| 14 | コミュニケーションにおける理解と表出の状況 | コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況(視覚、聴覚等の能力、言語・非言語における意思疎通)、コミュニケーション機器・方法等(対面以外のコミュニケーションツール(電話、PC、スマートフォン)も含む)に関する項目 |
| 15 | 生活リズム | 1日及び1週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度(活動の内容・時間、活動量等)、休息・睡眠の状況(リズム、睡眠の状況(中途覚醒、昼夜逆転等)等)に関する項目 |
| 16 | 排泄の状況 | 排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状況等、後始末の状況等、排泄リズム(日中・夜間の頻度、タイミング等)、排泄内容(便秘や下痢の有無等)に関する項目 |
| 17 | 清潔の保持に関する状況 | 入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況(皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等)、寝具や衣類の状況(汚れの有無、交換頻度等)に関する項目 |
| 18 | 口腔内の状況 | 歯の状態(歯の本数、欠損している歯の有無等)、義歯の状況(義歯の有無、汚れ・破損の有無等)、かみ合わせの状態、口腔内の状態(歯の汚れ、舌苔・口臭の有無、口腔乾燥の程度、腫れ・出血の有無等)、口腔ケアの状況に関する項目 |
| 19 | 食事摂取の状況 | 食事摂取(栄養、食事回数、水分量等)に関する項目食事摂取の状況(食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準備をする人等)、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量(栄養、水分量等)、食事制限の有無に関する項目 |
| 20 | 社会との関わり | 家族等との関わり(家庭内での役割、家族等との関わりの状況(同居でない家族等との関わりを含む)等)、地域との関わり(参加意欲、現在の役割、参加している活動の内容等)、仕事との関わりに関する項目 |
| 21 | 家族等の状況 | 本人の日常生活あるいは意思決定に関わる家族等の状況(本人との関係、居住状況、年代、仕事の有無、情報共有方法等)、家族等による支援への参加状況(参加意思、現在の負担感、支援への参加による生活の課題等)、家族等について特に配慮すべき事項に関する項目 |
| 22 | 居住環境 | 日常生活を行う環境(浴室、トイレ、食事をとる場所、生活動線等)、居住環境においてリスクになりうる状況(危険個所の有無、整理や清掃の状況、室温の保持、こうした環境を維持するための機器等)、自宅周辺の環境やその利便性等について記載する項目 |
| 23 | その他留意すべき事項・状況 | 利用者に関連して、特に留意すべき状況(虐待、経済的困窮、身寄りのない方、外国人の方、医療依存度が高い状況、看取り等)、その他生活に何らかの影響を及ぼす事項に関する項目 |
アセスメントシートの様式
アセスメントシートの様式は、ケアマネジメントに係る団体等が上記の23個の項目を網羅しつつ、更に必要な情報を集めるためや使いやすいように考え、それぞれの様式を作成しています。
これらの様式から自社が使いやすい様式を選択して使用することになりますが、「第15回社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会」(平成30年3月5日)の資料によると、居宅介護支援事業所の主に使用しているアセスメント様式は以下のようになっています。
| アセスメント様式 | 割合(%) |
|---|---|
| 居宅サービス計画ガイドライン方式 | 37.6% |
| 独自様式 | 19.2% |
| MDS方式・MDS-HC方式 | 15.4% |
| 包括的自立支援プログラム方式 | 4.3% |
| TAI方式・TAI-HC方式 | 2.1% |
| 日本介護福祉士会方式 | 1.5% |
| ケアマネジメント実践記録様式 | 0.8% |
| インターライ方式 | 0.7% |
| 日本訪問看護振興財団方式 | 0.5% |
| R4 | 0.3% |
| その他 | 12.5% |
| 名称不明 | 5.2% |
2.アセスメントシートの項目と書き方
ここでは、「居宅サービス計画ガイドライン方式」のアセスメントシート様式を例に、項目と書き方をご紹介します。
また、フェースシートに係る部分の項目や書き方は
こちらの記事
をご覧ください。
家族状況とインフォーマルな支援の状況
家族構成と介護状況
家族構成図
利用者の家族構成について、マークなどを使用し、構成図を作成します。
家族の介護の状況・課題
利用者の介護について、家族が行っている内容や状況、課題を記載します。
家族の氏名・続柄等
家族の氏名、性別、利用者本人との続柄、同居・別居の状況、就労の状況、健康状態等を記載します。また、主たる介護者には、氏名の横に『※』をつけます。
インフォーマルな支援活用状況
支援提供者・活用している支援内容等
活用しているインフォーマルな支援の内容と支援提供者等を記載します。
本人が受けたい支援・支援提供者等
利用者本人が受けたい支援や今後必要となると思われる支援の内容と支援提供者等を記載します。
サービス利用状況
在宅利用
利用をしている介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業等について、チェックをつけ、サービスの利用回数等を記載します。福祉用具貸与は調査日時点の品目数を、特定福祉用具販売は過去6ヵ月の品目数を記載し、住宅改修は、利用の有無に丸をつけます。
直近の入所・入院
直近に入所・入院している場合、該当する施設等の種類にチェックをつけ、施設・機関名、所在地、電話番号を記載します。
制度利用状況
利用者が現在利用している制度にチェックをつけます。
住居等の状況
戸建て・集合住宅、賃貸・所有・社宅等・公営住宅などから住宅の状況を選択し、居室やトイレ、浴室、設備、住居内での移動の状況についてチェックを記載します。
また家屋について段差などがわかるように見取り図を作成します。
本人の健康状態・受診等の状況
既往歴・現症
要介護状態に関係がある既往歴および現症を記載します。
身長・体重・歯の状況
身長、体重、歯の状況について記載します。
障害等の部位
障害や欠損、褥瘡がある部位について、正面、背面それぞれにマークを記入します。
病気やけが、障害等に関わる事項
病気やけが、障害等に関わる事項は特記事項として、改善の可能性等と併せて記載します。
現在の受診状況
利用者が現在、通院している場合には、病名、薬の有無、発症時期、受診頻度、受診状況、医療機関、診療科、主治医、連絡先、受診方法、留意点等を記載します。
また、往診可能な医療機関、緊急入院できる医療機関、かかりつけ薬局の有無にチェックをつけ、「有」の場合には、医療機関名・薬局名と電話番号を記載します。
生活上配慮すべき課題
生活上配慮すべき課題などの特記事項があれば記載します。
本人の基本動作等の状況と援助内容の詳細
基本(身体機能・起居)動作
要介護認定項目の基本動作について、該当する番号に丸をつけます。
麻痺や拘縮に該当する場合、洗身の項目に該当する場合、視力・聴力の項目に該当する場合は、援助の現状や希望、援助の計画、解決すべき課題などについて記載します。
生活機能(食事・排泄等)
要介護認定項目の生活機能について、該当する番号に丸をつけます。
移乗、移動、えん下、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪、上衣の着脱、ズボン等の着脱、外出頻度の項目に該当する場合は、援助の現状や希望、援助の計画、解決すべき課題などについて記載します。
【利用者説明用】訪問介護でできること・できないことガイドをご用意しています。
今すぐ無料でダウンロード→
認知機能、精神・行動障害
要介護認定項目の認知機能、精神・行動障害について、該当する番号に丸をつけます。
認知機能、精神・行動障害について、家族等からの情報と観察した内容、援助の現状、援助の希望(本人・家族)、援助の計画、解決すべき課題などを記載します。
社会生活
要介護認定項目の社会生活について、該当する番号に丸をつけます。
金銭の管理、買い物、、簡単な調理、電話の利用、日中の活動状況等の項目に該当する場合は、援助の現状、援助の希望、援助の計画、社会活動の状況、緊急連絡・見守りの方法、解決すべき課題などについて記載します。
医療・健康関係
要介護認定項目の医療・健康関係について、該当する番号に丸をつけます。
測定・観察、薬剤の管理、薬剤の使用、受診・検査介助、リハビリテーション、医療処置の管理について、援助の現状、希望、援助の計画、具体的内容、生活上配慮すべき課題、介護に関する医師の意見などを記載します。
全体のまとめ
アセスメントの内容のまとめを記載します。
また、災害時の対応や権利擁護の必要性について、必要性の有無に丸をつけ、災害時対応の必要性が有の場合には、災害時に連絡する方の氏名、利用者本人との関係、電話番号、FAX番号、メールアドレス等を記載します。
1日のスケジュール
1日のスケジュールについて、本人の生活リズム、本人が自分でしていること、本人がしたいと思っていること、援助の現状、要援助の判断などを、時間帯ごとに記載します。
3.アセスメントの実施にあたり注意する点とは?
ここでは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがアセスメントを行う際の注意点をいくつかご紹介します。
アセスメントの実施時間
アセスメントを実施する時間は「1~2時間ほど」を目安にしている事業所が多いようです。
アセスメントを実施する日は利用者とその家族と面談を行い、アセスメントシートの項目を網羅するために様々な情報を聞き取る必要があります。そのため、目安としている時間を超えてしまうこともありますが、皆さん自身のその後のスケジュールや利用者・家族のその後のスケジュールや疲労にも影響するので、できるだけ目安の時間内に終わるように効率良く実施することが求められます。
ただし、効率的に行うだけではなく、利用者やその家族が話しやすい雰囲気を作ることや得るべき情報の確認不足などには注意する必要があります。
可能な限り詳細に聞き取る
アセスメントでは、家族構成や家族の状況、年金、住居等の状況などを確認します。利用者の中には、家族との関係が良好ではない場合や家族に頼れない状況である場合に、その情報を伝えたくないと思う人、年金などの金銭面の状況を知られたくないと思う人、住居のあちこちを他人に見られたくない思う人もいます。
そのような状況の場合は、配慮する言葉を挟みながら詳細な情報を集めるのが良いでしょう。詳細な情報を集めることは、支援の質の向上や後々のトラブルを回避することに繋がります。
主治医意見書
健康状態を把握するためには、主治医意見書から情報を転記することが一般的です。そのためアセスメントに必要な書類となっていますので、取り寄せするのが遅れないように気をつけましょう。
4.まとめ
この記事では、全国社会福祉協議会の「居宅サービス計画ガイドライン」に沿ったアセスメントシートの様式を例に説明してきました。
アセスメントシートは、居宅介護支援サービス・介護サービスを利用するにあたって実施する「アセスメント」で使用する重要な書類です。
様々な団体からアセスメントシートの様式が作成されていますので、もし機会があれば今まで使ったことがないアセスメントシートの様式を検索して、内容を確認してみるのも良いと思います。
最後に、フェースシートの基本情報を始め、アセスメントシートの情報はその後のケアマネジメント業務において参照する情報となっています。これらの情報は転記することになるので、転記の効率化、転記によるミスを防止するためにも、介護請求ソフトをまだ導入していない事業所様は、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
5.アセスメントシートの様式の無料ダウンロード
アセスメントシートの様式は、『各種帳票の様式ダウンロードはこちら(無料)』からダウンロードできます。
帳票に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト