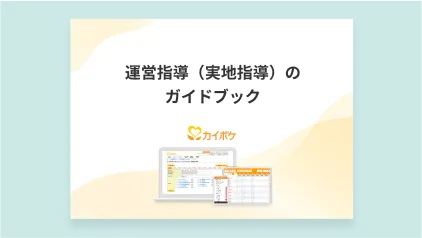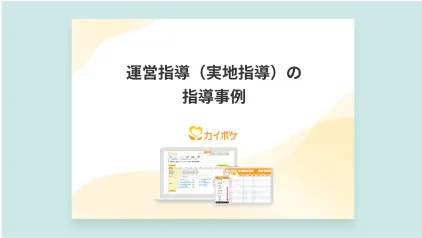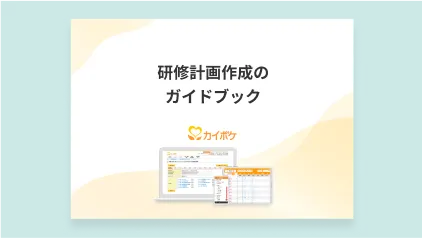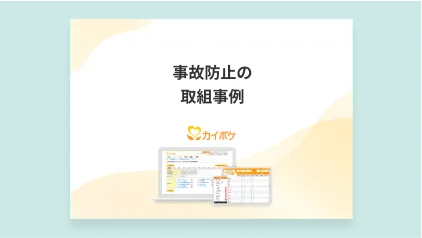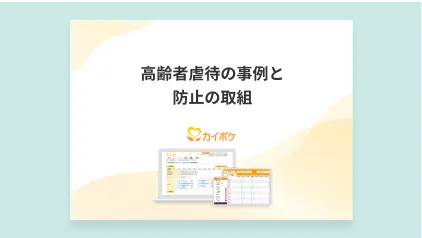訪問介護で会計・経理を効率化する方法とは?業務の流れやルールについても解説
訪問介護事業者の皆様は、日々の業務が忙しく、会計・経理業務を負担に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そのような中で、「会計・経理業務を効率化する方法はないの?」や「運営基準に書いてあることってどういう意味なの?」と悩んでいるのではないでしょうか。
この記事では、訪問介護事業所における会計・経理業務の流れやルール、効率的に会計・経理業務を行う方法などについて解説していきます。
目次
訪問介護で会計を行う目的とは?
会計は、資産・負債、収益・費用の動きを帳簿に記載(仕訳)して、決算書を作成するまでの一連の業務のことを言います。
会計業務を行う目的は、
- 出資者など、対外的な説明資料を作るため
- 経営者や管理者が事業の継続性や成長性などを判断する資料を作るため
- 納めるべき税金を適切に計算するため
といったことが挙げられます。
会計と経理の違いとは?
会社は資産・負債等と収益・費用の情報を対外的に発信・報告するために決算書を作成します。
そして、決算書を作成するために会計や経理といった業務を行うことになります。同じような業務として認識されていますが、会計と経理は業務の範囲に違いがあります。経理は、請求書の発行・入金確認、取引先への支払いなど、出入金について管理を行います。一方、会計は、企業が行った活動について記録し、決算書を作成するために必要なことを行います。
それでは、それぞれの業務について詳しく見ていきましょう。
会計の業務内容とは?
訪問介護では、以下のような会計業務を行います。
- 取引の内容を帳簿に記帳する。
- 帳簿の内容を会計ソフトに入力する。
- 月次決算書を作成する。
- 固定資産管理表などの帳簿を管理する。
- 決算書を作成する。
- 法人税申告書を作成し、提出する。
経理の業務内容とは?
訪問介護では、以下のような経理業務を行います。
- 現金の出納、残高を管理し、帳簿に記載する。
- 取引の内容に基づき、出金・振込等を行う。
- 介護報酬を請求する。
- 利用者負担金について請求書を発行する。
- 利用者負担金の回収状況の管理をする。
訪問介護の運営基準で定められた会計のルールとは?
訪問介護の会計で理解しておかなければならないルールが、運営基準で定められている「会計の区分」です。
(会計の区分)
第38条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
事業ごとに会計を区分することによって、どの事業が好調なのか数字を見て判断ができるようになります。
また、「介護事業の会計が他事業の会計と区分されていない」や「介護事業の収入は他事業の会計と区分しているが、支出を区分していない」という場合、運営指導(実地指導)で指導を受ける恐れがあるため、注意が必要です。
運営基準を満たす適切な会計処理方法として、具体的には以下の4つの方法が挙げられます。
- 会計単位分割方式
- 本支店会計方式
- 部門補助科目方式
- 区分表方式
会計単位分割方式とは?
会計単位分割方式とは、事業所単位ごとの介護サービス事業別に、あたかも別の法人のように仕訳帳や総勘定元帳をそれぞれ分ける方法です。
総勘定元帳が事業所単位ごとになるので、損益計算書・収支計算書・正味財産増減計算書も貸借対照表とともに事業所単位ごとに作成します。
本支店会計方式とは?
本支店会計方式とは、仕訳帳や総勘定元帳の一部について、事業所単位ごとの介護サービス事業別に分離して会計処理をする方法です。
事業所単位で損益計算書・収支計算書・正味財産増減計算書や貸借対照表は作成しますが、貸借対照表の資本の部(純資産の部)については分離せず、いわゆる本支店区分だけ存在させます。
本部あるいは他の事業所間の取引は、本支店勘定(貸借勘定)で処理をします。
部門補助科目方式とは?
部門補助科目方式とは、勘定科目に補助コードを設定し、仕訳時に補助コードを記入することで、介護サービス事業別の数値が集計できるようにする方法です。
貸借対照表は介護サービス事業別の区分をせず、損益計算書・収支計算書・正味財産増減計算書は区分します。
区分表方式とは?
区分表方式とは、仕訳時に区分をせず、それぞれの科目に按分基準を設け、配分表によって介護サービス事業別の結果表を作成する方法で、以下の流れで行います。
- 通常の決算書類を作成する。
- 売上高を、事業拠点・サービスごとに配分する。
- 経費を、共通費と個別費に分類する。
- 共通費の按分率を設定する。
- 共通費に按分率をかけて、各区分に配分する。
- 各区分に配分された売上および経費を集計する。
共通費と個別費の例
複数事業所・サービスにまたがる費用が共通費、各サービスがそのサービスを行うために直接必要な費用が個別費です。
以下の表は、共通費と個別費の例です。
【共通費】
- 総会や理事会の開催運営費
- 事務所の家賃
- 事務所の光熱費
- 借入金の利息
- 役員報酬
- 複数事業所を兼務するヘルパーの給料
【個別費】
- 各事業所専属のヘルパーの給料
- 各事業所における研修参加費
勘定科目と按分の方法とは?
具体的な勘定科目と按分方法は、以下の表のようになっています。
| 種類 | 勘定科目 | 按分方法 |
|---|---|---|
| 給与費 | 介護職員・医師・看護婦給与等常勤職員給与
介護職員・医師・看護婦給与等の非常勤職員給与 退職給与引当金繰入 法定福利費 |
勤務時間割合により区分する。
(困難な場合は次の方法により按分)
|
| 材料費 | 介護用品費
医薬品費 施設療養材料費 施設療養消耗器具備品費 診療材料費 医療消耗器具備品費 |
各事業の消費金額により区分する。
(困難な場合は次の方法により按分)
|
| 給食用材料費 | 実際食数割合により区分する。
(困難な場合は次の方法により按分)
|
|
| その他の材料費 | 延利用者数割合により按分する。
(困難な場合は各事業別の収入割合により按分) |
|
| 経費 | 福利厚生費
職員被服費 |
給与費割合により区分する。
(困難な場合は延利用者数割合により按分) |
| 旅費交通費
通信費(通信運搬費) 交際費 諸会費 雑費 渉外費 |
|
|
| 消耗品費
消耗器具備品費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 広報費 |
各事業の消費金額により区分する。
(困難な場合は延利用者数割合により按分) |
|
| 車両費 | 使用高割合により区分する。
(困難な場合は次の方法により按分)
|
|
| 会議費 | 会議内容により事業個別費として区分する。
(困難な場合は延利用者数割合により按分) |
|
| 光熱水費 | メーター等による測定割合により区分する。
(困難な場合は建物床面積割合により按分) |
|
| 修繕費(修繕維持費) | 建物修繕は、当該修繕部分により区分、建物修繕以外は事業個別費として按分する。
(困難な場合は、建物床面積割合で按分) |
|
| 賃借料
地代家賃等 |
賃貸物件特にリース物件については、その物件の使用割合により区分する。
(困難な場合は、建物床面積割合により按分) |
|
| 保険料 |
|
|
| 租税公課 |
|
|
| 保守料 | 保守契約対象物件の設置場所等に基づき事業個別費として区分する。
(困難な場合は延利用者数割合により按分) |
|
| 委託費 | 委託費(寝具)(給食)(その他) | 各事業の消費金額により区分する。
(困難な場合は延利用者数割合により按分)
|
| 研修費 | 謝金
図書費 旅費交通費 研修雑費 研究材料費 |
研修内容等、目的、出席者等の実態に応じて、事業個別費として区分する。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
| 減価償却費 | 建物減価償却費
建物附属設備減価償却費 構築物減価償却費 |
建物床面積割合により区分する。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
| 医療用器械備品減価償却費 | 使用高割合により区分する。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
|
| 車両船舶減価償却費 | 使用高割合により区分する。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
|
| その他の器械備品減価償却費 | 使用高割合により区分する。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
|
| その他の有形固定資産減価
償却費 無形固定資産減価償却費 |
延利用者数割合により按分する。 | |
| 徴収不能額 | 徴収不能額 | 各事業の個別発生金額により区分する。
(困難な場合は各事業別収入割合により按分) |
| 引当金繰入額 | 退職給与引当金繰入
賞与引当金繰入 |
給与費割合により区分する。
(困難な場合は延利用者数割合により按分) |
| 徴収不能引当金繰入 | 事業毎の債権金額に引当率を乗じた金額に基づき区分する。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
|
| 支払利息 | 支払利息 | 事業借入目的の借入金に対する期末残高割合により区分する。
(困難な場合は、次の方法により按分)
|
介護保険の給付対象事業における会計の区分について (平成13年3月28日老振発第18号)より作成
訪問介護の会計を効率化する方法とは?
会計業務を適正かつ効率的に行うためには、
- 利用者負担金の回収を口座振替にする
- 介護事業所向けの会計ソフトを導入
- 訪問介護に詳しい税理士に相談をする
といった方法が考えられます。
利用者負担金の回収を口座振替にする
利用者負担金の回収に関する業務が重荷になっているケースがあります。
現金での回収をやめて口座振替に切り替えると、利用者様からの集金業務の手間を省くことができます。
また、請求ソフトと利用者負担金の口座引落の機能が連動している請求ソフトを導入すると、計算した請求データから直接口座引落のデータを作成し、送信することができるのでとても便利です。
介護事業所向けの会計ソフトを導入
ソフトの種類にもよりますが、会計ソフトを導入すると以下のようなメリットがあります。
【会計ソフトを導入するメリット】
- 銀行やクレジットカードと連携させることで、入力や仕訳を自動化し、データ入力の手間を削減できる。
- 仕訳で入力したデータから、キャッシュレポートや決算書などが自動で作成されるため、レポート作成の手間が省ける。
- 外部委託していた時よりもスピーディーにレポートを作成できる。
訪問介護の経理・会計ソフトはカイポケ会計がおすすめ
訪問介護の経理・会計ソフトは、「カイポケ会計・労務 by Money Forward クラウド会計」がおすすめです。
介護保険請求・記録ソフトのカイポケ会員なら、月額基本料金0円から利用可能です。ご興味のある方は、ぜひこちらから詳細をご覧ください。
訪問介護に詳しい税理士に相談をする
ご自身の事業所で作成している決算書が、「訪問介護の運営基準に定められた『会計の区分』を遵守したものになっているのだろうか?」と不安を感じる方は、訪問介護に詳しい税理士に一度相談してみるのもいいかもしれません。
【税理士に相談するメリット】
- 運営基準に定められた会計の区分を満たすための会計・経理業務のルール作りをすることができる。
- 運営基準を満たしつつ、より効率的に会計・経理業務をするための体制構築をすることができる。
まとめ
ここまで、訪問介護事業所における会計の目的や、会計・経理業務の流れなどについて述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
訪問介護事業所では、日々の業務が忙しいために、会計や経理業務を適切に行うことが難しいかもしれません。ルールを遵守し、運営指導(実地指導)で指摘を受けないためにも、介護事業向けの会計ソフトを導入していない場合は、導入・切り替えを検討してみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト