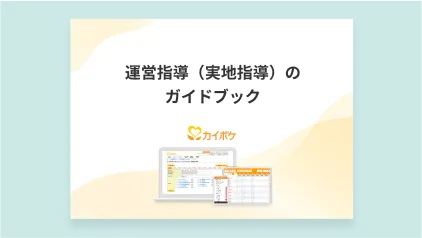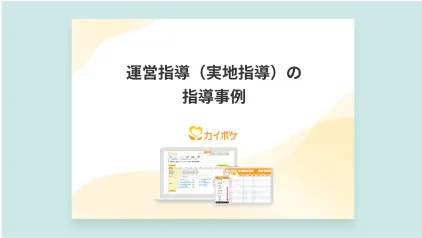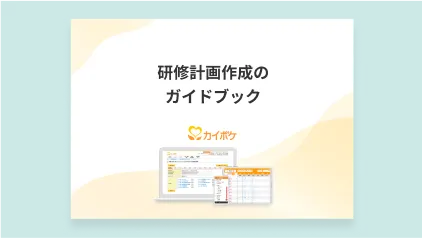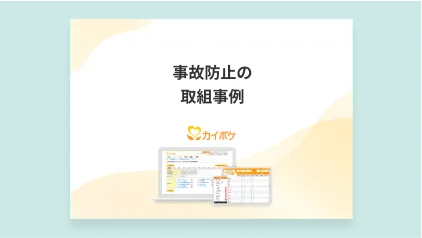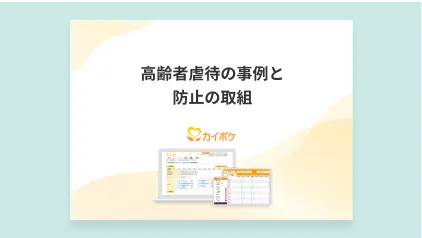訪問介護(ヘルパー)の離職率の平均はどのくらい?職員定着のための方法もご紹介
訪問介護事業では、訪問介護員の人数を確保することで、サービス提供の時間や回数を増やすことができるので、「離職を減らし、採用を進めること」がとても大切です。
経営者や管理者の皆様は、「離職率ってどうやって計算するの?」や「うちの離職率は全国平均と比較して高いの?」、「離職率を下げるためにはどうすればいいの?」などといった疑問や悩みをお持ちではないでしょうか。
そのような皆様に向けて、この記事では、離職率の算定方法や、職員が離職を考える理由、離職率を下げるための対策について解説していきます。
目次
訪問介護の離職率の平均は?
介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査結果」によると、(主とする介護サービスが)訪問介護における離職率は以下のようになっています。
- 訪問介護員:12.1%
- サービス提供責任者:7.7%
また、訪問介護事業所における平均勤続年数は『8.1年』となっています。
離職率の計算方法
離職率は、以下のような計算式で算出することができます。
離職率=1年間の離職者数÷(調査時点の在籍者数-採用者数+離職者数)×100
平均勤続年数の計算方法
平均勤続年数は、以下のような計算式で算出することができます。
平均勤続年数=常勤職員の勤続年数の合計÷常勤職員の総人数
訪問介護のヘルパー・サ責が離職する理由とは?
訪問介護の従業員は、どのような理由で離職や転職を考えるのでしょうか。
介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査結果」によると、訪問介護の「前職をやめた理由」は以下のようになっています。(その他・無回答は除外)
| アンケート項目 | 回答の% |
|---|---|
| 職場の人間関係に問題があったため | 33.6% |
| 法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため | 26.3% |
| 他に良い仕事・職場があったため | 22.1% |
| 収入が少なかったため | 18.2% |
| 自分の将来の見込みが立たなかったため | 14.2% |
| 結婚・妊娠・出産・育児のため | 8.4% |
| 人員整理・推奨勧告・法人解散・事業不振等のため | 7.3% |
| 新しい資格を取ったから | 4.8% |
| 自分に向かない仕事だったため | 4.0% |
| 家族の介護・看護のため | 4.0% |
| 家族の転職・転勤、又は事業所の移転のため | 3.2% |
| 病気・高齢のため | 3.0% |
| 定年・雇用契約の満了のため | 2.3% |
訪問介護で離職を減らして定着率を上げるための対策とは?
訪問介護で離職を減らし、定着率をあげるためには、職場への不満や不安を少なくしていくことが大切です。
そのために、先ほどご紹介した離職する理由と合わせて、「人間関係の悩み」と「労働条件等の悩み、不安、不満等」の具体的な内容も把握する必要があります。
介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査結果」によると、訪問介護の「人間関係の悩み」と「労働条件等の悩み、不安、不満等」の具体的な内容は以下のようになっています。
【人間関係等の悩み】
- 上司の思いやりのない言動、きつい指導、パワハラなどがあった
- 上司の管理能力が低い、業務指示が不明確、リーダーシップがなく信頼できなかった
- 同僚の言動(きつい言い方・悪口・嫌み・嫌がらせなど)でストレスであった
- ケアの方法など仕事上の課題に関する上司や同僚との意思疎通・意見交換が上手くいかなかった
【労働条件等の悩み】
- 人手が足りない
- 仕事内容のわりに賃金が低い
- 有給休暇が取りにくい
- 休憩が取りにくい
- 身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安がある)
- 健康面(新型コロナウイルス等の感染症、怪我)の不安がある
- 業務に対する社会的評価が低い
- 精神的にきつい
離職率を下げ、定着率を上げるための取り組み例
離職理由と人間関係等の悩み、労働条件の不満等を考慮すると、離職率を下げるために、以下のような方法が有用だと思われます。
- ハラスメント対策に取り組む。
- リーダーシップ研修等を行い、リーダーの育成に取り組む。
- 意思疎通や意見交換をスムーズにするためのソフトやツールを導入する。
- 業務負担が大きくなり過ぎないように、従業員を採用する。
- 算定する加算を増やす、または上位区分の加算を算定して、賃金アップを行う。
- 残業を少なくし、有給休暇を取りやすくする等の職場の環境・雰囲気の改善に取り組む。
まとめ
訪問介護の離職率の計算方法や離職率の全国平均、離職率を下げるための対策についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
「離職率が高い」と感じている場合は、職員が辞める理由と近隣の介護事業所の求人情報などを調査し、労働条件や給与水準の改善、働きやすい職場環境の構築を検討しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト