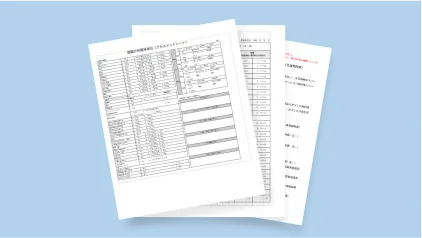【無料ひな型】訪問介護のアセスメントシートとは?書き方のポイントや項目を解説
訪問介護に従事される方の中には「アセスメントシートの書き方のポイントは?」「アセスメントシートに記載すべき内容は?」など疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では訪問介護のアセスメントを行わなければいけない理由、アセスメントシートの主な項目、記入する際のポイントなどを解説します。
ぜひ最後までお読みください。
目次
- 訪問介護のアセスメント
- 訪問介護のアセスメントシートとは?
- アセスメントシートに記載する主な項目
- 訪問介護のアセスメントシートの書き方【3つのポイント】
- 【無料】訪問介護アセスメントシートのひな型・テンプレートをダウンロード
- まとめ
訪問介護のアセスメント
訪問介護のアセスメントとは?
訪問介護におけるアセスメントとは、利用者様の心身の状態や生活環境、本人・家族の希望などの情報を、「何ができるのか」「何に困っているのか」「どんな支援があれば理想の生活に近づくのか」といった視点からヒアリングを行い、状況・課題の把握・分析することです。
アセスメントはサービスを開始する前に実施し、アセスメントの情報をもとに利用者様に適した訪問介護サービスを計画します。
また、サービスの開始前だけでなく、状態の変化や環境の変化があった場合には随時アセスメントを実施し、計画を見直します。
アセスメントを行わなければいけない理由
訪問介護では、必ずアセスメントを実施する必要があります。
厚生労働省が定める運営指導で確認される『確認項目及び確認文書』においても明記されています。
| 確認項目 | 確認文書 | |
|---|---|---|
| 訪問介護計画の作成
(第 24 条) |
・居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか
・利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか ・サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか ・利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか ・目標の達成状況は記録されているか ・達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか |
・居宅サービス計画
・訪問介護計画 (利用者又は家族の 同意があったことがわか るもの) ・アセスメントシート ・モニタリングシート |
つまり、訪問介護事業者は利用者の心身の状況、希望および環境の把握(=アセスメント)を行い、アセスメントの記録(アセスメントシート等)を保管しておく必要があります。
訪問介護のアセスメントシートとは?
アセスメントシートとは、アセスメントを行った日時、場所、利用者様に関して得た情報などを記載する書類です。
訪問介護計画の作成・見直しなどの際に使用します。
また、アセスメントシートは、アセスメントを実施したことを証明する書類でもあり、運営指導では「確認文書」として提出が求められることがあります。
訪問介護においてアセスメントシートは、利用者様に合った支援を行うための土台となる非常に重要な書類です。
アセスメントシートに記載する主な項目
訪問介護のアセスメントシートの様式は定められていません。
そのため、各事業所が方針に合わせて、必要な情報を適切に把握できるようなフォーマットを用意して使っています。
ここでは、訪問介護のアセスメントにおいて記載する主な項目を例としてご紹介します。
基本情報に関する項目
| 基本情報に関する項目 | 記載する内容 |
|---|---|
| 基本情報(受付、利用者等基本情報) |
|
| これまでの生活と現在の状況 |
|
| 利用者の社会保障制度の利用情報 |
|
| 現在利用している支援や社会資源の状況 |
|
| 日常生活自立度(障害) |
|
| 日常生活自立度(認知症) |
|
| 主訴・意向 |
|
| 認定情報 |
|
| 今回のアセスメントの理由 |
|
課題分析(アセスメント)に関する項目
| 課題分析(アセスメント)に関する項目 | 記載する内容 |
|---|---|
| 健康状態 |
|
| ADL |
|
| IADL |
|
| 認知機能や判断能力 |
|
| コミュニケーションにおける理解と表出の状況 |
|
| 生活リズム |
|
| 排泄の状況 |
|
| 清潔の保持に関する状況 |
|
| 口腔内の状況 |
|
| 食事摂取の状況 |
|
| 社会との関わり |
|
| 家族等の状況 |
|
| 居住環境 |
|
| その他留意すべき事項・状況 |
|
訪問介護のアセスメントシートの書き方【3つのポイント】
訪問介護のアセスメントシートを書く際には、以下の3つのポイントを意識して記入するとよいでしょう。
- 「できること」も明確に記載する
- 主観や推測ではなく「事実」に基づいて記録する
- 訪問介護計画につながることを意識する
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
「できること」も明確に記載する
アセスメントでは「何ができないか」だけではなく「何ができるか」も正確に記載することが重要です。
例えば、「調理は難しいが、食器の準備はできる」「外出は付き添いが必要だが、室内での移動は可能」など、できる範囲と支援が必要が範囲を切り分けて記載することで、利用者様の自立している部分を尊重しつつ、適切な支援を提供することが可能になります。
主観や推測ではなく「事実」に基づいて記録する
アセスメントシートでは、「事実」に基づいた客観的な内容・表現であることが大切です。
主観的な印象や曖昧な表現は避け、客観的な内容・表現での記載を心がけましょう。
例えば、「元気そう」と曖昧な表現で書くのではなく、「受け答えがはっきりしており、質問にも即答していた」など、具体的な言動をもとに記載します。
訪問介護計画につながることを意識する
アセスメントシートの記録は、訪問介護計画の元となる大切な情報です。
利用者の状態を把握するだけではなく、具体的にどのような支援が必要か判断するためのプロセスであることを意識しましょう。
「この情報からどんな支援が必要だと判断できるか」を意識しながら記載することで、実際の支援につながるアセスメントシートになります。
【無料】訪問介護アセスメントシートのひな型・テンプレートをダウンロード
訪問介護アセスメントシートのひな型は下記より無料でダウンロードいただけます。
ぜひご活用ください。
まとめ
ここまで、訪問介護のアセスメントを行わなければいけない理由、アセスメントシートの主な項目、記入する際のポイントを解説してきました。
アセスメントシートは利用者様の支援方針を決めるために聴き取った情報を記載する大切な書類になります。
適切に抜けもれなく情報収集ができるよう、事業所に合ったフォーマットを使用しましょう。
本記事ではアセスメントシートのひな型・テンプレートのダウンロードいただくことも可能なので、ぜひご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
帳票に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト