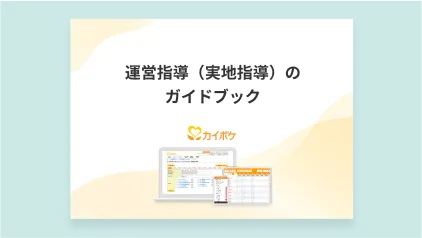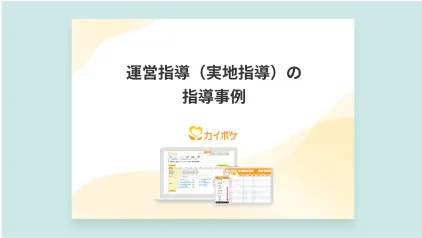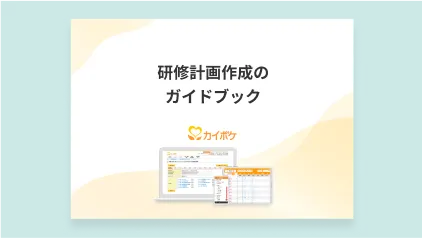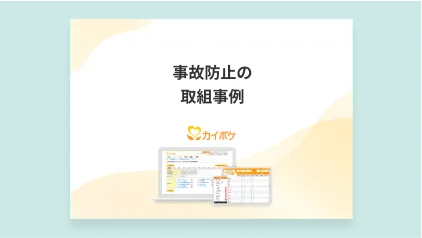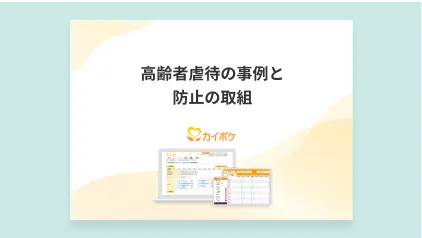訪問介護の人事考課とは?評価の流れやポイントを解説!
訪問介護の経営者・管理者の中には「人事考課の目的は?」「人事考課はどのような流れで行うの?」「人事考課で注意すべきポイントは?」などの疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、訪問介護の人事考課の目的や方法、人事考課のメリットや注意点を解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
目次
訪問介護における人事考課の目的は?
人事考課とは
人事考課とは、職員一人ひとりの勤務態度や業務遂行能力、成果などを一定の基準に沿って評価する仕組みのことを指します。
訪問介護では、コミュニケーション力や介護スキルなどを評価の項目としていることが多いです。
人事考課の目的
人事考課の目的は、職員を公正に評価し、その評価をもとに処遇(給与・賞与・昇進など)を決定することです。
公正な評価、処遇の決定は、職員の成長やサービスの向上、職場環境の改善にも繋がります。
訪問介護における人事考課の流れは?
人事考課は次のような流れで実施します。
- 評価基準の設定
- 各職員の目標設定
- 考課面談の実施
- 処遇の反映とフィードバック
それぞれ詳細を見ていきましょう。
1.評価基準の設定
まずは、職員を評価するための基準(評価基準)を設定します。
雇用形態等によって異なりますが、厚生労働省『職業能力評価シート(在宅介護業)』を参考にすると、訪問介護では下記のような項目に対して評価基準を設定すると良いでしょう。
- 企業倫理とコンプライアンス
- チームワークとコミュニケーション
- 外部、関係機関との連携
- 目標管理
- 利用者の安全確保、トラブルの未然防止
- 初回サービスのための準備
- 訪問介護サービスの実施
- サービスの検証
- 利用者への情報提供
- スタッフの指導・育成
- 移動・移乗介助、体位交換、外出介助
- 食事介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- 身体整容
- 調理
- 洗濯
- 掃除
- 買い物代行
参考:厚生労働省『職業能力評価シート(在宅介護業)のダウンロード』
2.各職員の目標設定
次に、職位、職務に応じて適切な目標を設定します。
短期的な目標と中長期的な目標を組み合わせて設定することで、職員の日常的な業務スキルの向上だけではなく、将来的なキャリア形成にも繋がります。
3.考課面談の実施
評価を決定する前に、職員と評価者で考課面談を実施します。
一般的には、考課面談は半年〜1年に1回ほどのサイクルで行います。
最終的な評価は、本人および評価者からの評価を総合して決定します。
4.処遇の反映とフィードバック
職員への評価が確定したら、その結果に応じて処遇を決定します。
また、評価と処遇の内容は職員へフィードバックしましょう。
人事考課を行うメリット
訪問介護で人事考課を行うメリットは次の通りです。
モチベーションの維持・向上
人事考課を行うことで、職員のモチベーションの維持や向上に繋がります。
「努力が正しく評価される」「頑張れば給与に反映される」といった安心感や期待感により日々の業務に対する意欲を高めることができます。
職員のスキル把握
人事考課は、管理者が職員のスキルを把握するために役立ちます。
職員一人ひとりのスキルを正しく把握することで、適切なマネジメントに繋がります。
サービスの質の向上
人事考課により、職員の能力や行動が可視化されることは、事業所全体のサービスの質の向上に繋がります。
また、職員が目標や評価を意識することで、日々のサービスの精度や利用者対応の質を高めることができます。
人事考課を行う際のポイントと注意点
人事考課を行う際のポイントや注意点は次の通りです。
評価基準を明確にする
評価基準は明確に設定しましょう。
曖昧な基準にすると、人により解釈が異なり、評価者が正当な評価をできない可能性や職員が正当に評価を受けられていないと感じてしまう可能性があります。
主観に偏らない
評価者は、主観に偏った評価をしないように注意しましょう。
評価者の個人的な感情(好き・嫌いなど)で評価をしたりせず、評価基準に沿った客観的な視点で評価をします。
複数の評価者による評価をするのも効果的です。
根拠を明確にしてフィードバックを行う
フィードバックを行う時は、結果だけではなく評価の根拠を伝えましょう。
面談を通じて「なぜその評価になったのか」を具体的に伝えることで職員の納得感を高めることができます。
まとめ
この記事では、訪問介護の人事考課の目的やメリット、注意点を解説してきました。
人事考課は、公正な評価による処遇を決定することで、職員のモチベーションやサービスの向上に繋がるという重要な役割があります。
評価基準や目標の設定、客観的な評価と具体的なフィードバックをすることが人事考課では大切なポイントです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト