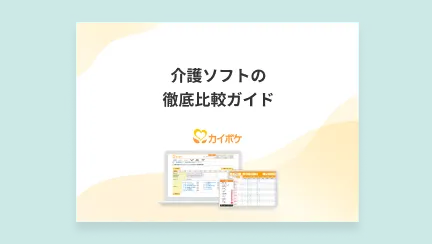訪問介護でタブレットを使うメリットは?導入方法やスマホとの違いも解説
訪問介護の運営や管理をする方の中には「訪問介護でタブレットを導入するメリットは?」「訪問介護でタブレットを導入するにはどうすればいいの?」「スマホとタブレットはどちらがいいの?」と疑問をお持ちの方も多いかと思います。
この記事では、訪問介護の現場でタブレットの導入する目的や方法、タブレット導入のメリット・デメリット、スマホとタブレットの違いや、タブレット導入時の注意点について解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
目次
- 訪問介護の現場でタブレットを導入する目的は?
- 訪問介護のタブレットの導入方法は?
- 訪問介護でタブレットを導入するメリット
- 訪問介護でタブレットを導入するデメリット
- 【比較】タブレットとスマホの違い・類似点は?
- タブレット導入時の注意点
- 訪問介護事業におススメなのは「スマホ」
- まとめ
訪問介護の現場でタブレットを導入する目的は?
訪問介護の現場でタブレットを導入する目的は、外出先でタブレットを使用して、訪問記録を効率的に作成したり、必要な情報を確認したりすることで、業務の効率化を図ることです。
そして、業務を効率化することは、職員の負担の軽減や職場環境の改善にもつながっているので、事業所として導入する価値があることだと言えます。
訪問介護のタブレットの導入方法は?
訪問介護の現場にタブレットを導入する方法は、大きく分けて以下の2つがあります。
- タブレットをレンタルする
- タブレットを購入する
それぞれにメリットとデメリットがあるので見ていきましょう。
タブレットをレンタルする
タブレットレンタルでは、定額料金でタブレットを導入することができます。
タブレットをレンタルするメリットは、タブレット本体代・通信料などが月額料金にすべて含まれているため、契約や管理の手間が少なく導入しやすい点です。
特に、職員の人数の変動により必要なタブレット台数が変わった際でも「契約しやすく、解約しやすいこと」から適切な契約台数に調整できるという点でレンタル契約が選ばれています。
また、故障時の交換対応やセキュリティ設定がされていることなども大きなメリットになっています。
一方、デメリットは、長期的に利用する場合にタブレットの購入よりコストが割高になる可能性があることです。
また、選択できる端末(OSやスペック)が限られており、使いたいアプリやツールに対応していないこともありますので注意しましょう。
タブレットを購入する
タブレットの本体を購入し、通信会社と契約することでタブレットを導入することができます。
タブレットの本体代は、一括または分割にて支払い、通信料などのプランを選びます。
メリットは、本体の機種、通信料のプランを自由に選択できるため、ランニングコストをコントロールしやすい点です。
また、タブレット本体を購入し一定期間故障などがなく使えると負担するコストが少なくなるという利点があります。
一方、デメリットは、初期設定やセキュリティ対策などをすべて事業所側で行う必要があるため、一定の知識や作業時間が必要になる点です。
訪問介護でタブレットを導入するメリット
メリット①記録の作成・管理が楽になる
介護ソフトと合わせてタブレットを導入することで、訪問記録の作成や管理を楽に行うことができます。
タブレットから直接介護ソフトに入力できるため、手書きよりも効率的に記録を作成できます。
また、記録データはそのまま保存されるため、紙への印刷やファイリングといった保管作業が不要になり、事務作業の負担軽減にもつながります。
さらに、訪問記録が実績に自動で反映されるため、紙からパソコンへ転記する手間や転記時のミスを減らすことができます。
メリット➁外出先でも情報をスムーズに確認や共有ができる
タブレットを利用することで、介護現場や外出先でも記録の入力や情報の確認・共有がスムーズに行えるようになります。
例えば、緊急で訪問することになったヘルパーが、利用者様の情報をタブレットから簡単に確認することや、利用者様の状態で気になる点があればタブレットからスムーズに記録・共有することができます。
メリット③災害時の対策になる
万が一、事業所が地震や水害、火災などに被災してしまったとしても、クラウド型の介護ソフトとタブレットを導入している場合は、データセンターにデータが保管されているのでデータを守ることができます。
また、災害時でも利用者情報やこれまでの記録を確認し、適切なサービスの提供につなげることができるので事業継続という視点でもメリットがあります。
訪問介護でタブレットを導入するデメリット
デメリット①操作に慣れるのに時間が必要
タブレットの使用に慣れていない職員がいる場合、操作に慣れるまでに時間がかかることがあります。
こうした職員にとっては、タブレットの導入が心理的な負担になったり、職場への不満につながったりする可能性も考えられます。
そのため、導入にあたっては事前の説明会や研修の実施、操作マニュアルの整備やサポート体制の構築などを検討することが重要です。
デメリット➁セキュリティ・個人情報保護の対策が必要
訪問介護では、利用者の氏名・住所・サービス内容などの個人情報を扱うことになるため十分なセキュリティ対策が必要になります。
タブレット上で個人情報を管理する場合、紛失や盗難に備えて、パスコードや指紋認証の設定、リモートロックの仕組みなど、十分なセキュリティ対策を行わなければいけません。
さらに、事業所から支給したタブレットの私用利用の制限などルールを明確にする必要があります。
デメリット③機器・システムの導入コストが必要
タブレットの導入には、レンタル費用または端末本体の購入費用、通信契約の導入コストなどが発生します。
また、導入後も毎月の通信費や保守費用、場合によってはツール・システム利用料などを継続的に支払う必要があります。
そのため、初期費用や月々にかかる費用などをあらかじめ計算した上で導入を検討しなくてはいけません。
【比較】タブレットとスマホの違い・類似点は?
タブレットとスマホの違い
タブレットとスマホでは、次のような違いがあります。
画面サイズの違い
タブレットとスマホでは画面のサイズが大きく異なります。
タブレットは画面が大きく、文字や画面全体が見やすいため記録作業や情報の確認がしやすくなります。
一方、スマホは画面が小さいので、タブレットに比べ文字も小さくなりますが、片手での操作ができるというメリットがあります。
入力の方法の違い
タブレットとスマホでは入力する際の方法が異なります。
タブレットは画面が大きいので、フリック入力(キーを指でスライドする方法)だけではなくキーボードでの入力や、手書き入力がしやすくなります。
スマホは画面が小さく、フリック入力やトグル入力(キーを複数回タップする方法)が主流です。
どちらが操作しやすいかは、個人の好みや慣れによるでしょう。
持ち運びやすさの違い
タブレットとスマホは大きさに違いがあります。
タブレットは本体サイズが大きくやや重みがあるので、持ち運びをする際に不便に感じる場合があります。
一方、スマホは本体サイズが小さく軽量のため、持ち運びが簡単です。
タブレットとスマホの類似点
タブレットとスマホの類似点は次の通りです。
介護ソフトを使った情報の確認や入力
クラウド型の介護ソフトであれば、タブレット・スマホのどちらからでも記録の入力や利用者情報の確認が可能です。
ヘルパーが訪問先で記録を入力できるため、転記の手間や記入漏れを防ぐことができます。
また、利用者様の情報の確認や申し送り事項も簡単に確認できるのでサービスの質向上にもつながります。
外出先での情報共有や連絡がスムーズ
どちらの端末でも、外出先でも職員間の情報共有がスムーズに行えます。
急な予定変更や利用者様の体調変化といった情報も、すぐに伝達・共有できることで、柔軟な対応が可能になります。
カメラ機能を使える
タブレット・スマホともにカメラ機能を搭載しているので、撮影した写真を訪問介護の記録や報告に役立てることができます。
例えば、利用者様に気になる傷等があり、その状態を文面で説明するのが難しい場合、カメラ機能を使い、記録に画像を添付することで情報が充実した記録を作成できます。
利用者家族やケアマネジャー、サービス提供責任者など関係者・関係職種への適切な情報共有が可能になるでしょう。
しかし、カメラ機能は便利な一方で、利用者様やご家族に不快な思いをさせてしまう場合もあります。
利用者様やご家族には事前に許可を取り、むやみな撮影は避けるように心掛けましょう。
音声入力で文章が作成できる
タブレットやスマホには音声入力機能が搭載されています
サービス提供中で手が離せないタイミングやタブレットでの直接入力よりも音声入力の方が早い場合などは、音声入力機能を活用することで記録の作成時間の短縮につながるでしょう。
タブレット導入時の注意点
職員へのサポート体制を作る
訪問介護でタブレットを活用するためには、タブレットに苦手意識を持つ職員へのサポート体制を作りましょう。
全ての職員がタブレットを活用できなければ、生産性の低下や職員の不満に繋がる可能性もあります。
タブレットに苦手意識を持っている職員に対しては、特に留意し、気軽に質問しやすい環境を整えるように注意しましょう。
セキュリティ対策を万全にする
訪問介護でタブレットを導入する際には、セキュリティ対策を万全にしておくよう注意しましょう。
タブレットを業務で運用する場合、利用者や職員の個人情報がタブレットで確認できるようになります。
セキュリティの対策を怠ると、利用者からの信頼を失うだけではなく、法的な罰を受ける可能性もあります。
そのため、事業所内で徹底したセキュリティ対策と職員への浸透が必要です。
具体的には、下記のような対策が挙げられます。
- タブレットには必ずパスワードや顔認証を設定する
- アプリやサイトへのアクセスに制限をかける
- 業務用のタブレットを私的利用しない
- 紛失・盗難時にGPSで探せるような設定・契約にする
- 紛失・盗難時に遠隔操作で端末をロックできるように設定する
コストを明確にする
タブレットを導入する際には、トータルコストを明確にしましょう。
レンタルするのかと、購入するのかでは初期費用が違ってきます。
また、外出先で使うためにはSIMカードが必要となり、月額の利用料金がかかります。
導入後の料金を明確にすることで、予算に合わせてタブレットを運用することが可能です。
タブレットの料金を比較する際は、
- 月額の利用料金(本体代と通信料)
- 何ギガまで高速通信できるのか
といった点も確認しましょう。
訪問介護事業におススメなのは「スマホ」
ここまでお読みいただいた方の中には、「タブレットとスマホ、訪問介護にはどちらが向いているの?」と気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、訪問介護の現場には 「スマホ」の活用をおすすめします。
スマホが訪問介護の現場に最適な理由は次の5点です。
- 日常生活でも利用していて、スマホを使い慣れている人が多い
- 格安スマホの選択肢があり、コストを抑えることができる
- タブレットより持ち運びがしやすく、外出が多いヘルパーに適している
- 電話かけ放題など、業務に合った幅広いプランが選べる
- 利用者様に画面を見せることが少ないため、大きい画面である必要がない
もちろん、タブレットにも画面の見やすさや入力のしやすさといったメリットがあります。導入を検討する際は、事業所の運営スタイルに合わせてスマホとタブレットの特性を比較することが大切です。
スマホの導入なら、介護の現場に最適なスマホを提供する『カイポケモバイル』が特におすすめなのでぜひご検討ください。
まとめ
ここまで、タブレットの導入方法やメリット・デメリット、スマホとタブレットの違いや、タブレット導入時の注意点について解説してきました。
タブレットを導入することで事務作業の効率化が望めるなどメリットがあります。
一方で、タブレットと比較しスマホの方が訪問介護の現場に適している点が多いためおすすめです。
スマホやタブレットは、スマホ・タブレットでも使える介護ソフトと一緒に導入しないと業務の効率化が実現できません。
まずは、現在お使いの介護ソフトがスマホ・タブレットでも使えるのかどうかを確認し、使えない場合は介護ソフトの乗り換えも含めて検討しましょう。
ソフト比較に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト