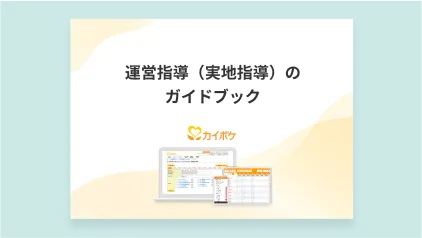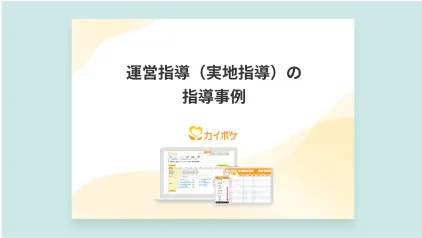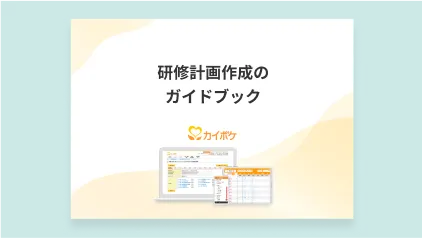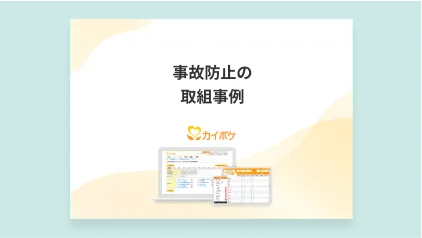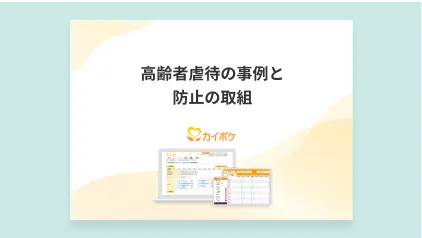【訪問介護】研修資料の作成方法と研修テーマ21選をご紹介!
訪問介護の経営・管理者の方の中には、「研修資料が上手く作成できない」「研修テーマはどうやって決めたらいいの」などお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、訪問介護の法定研修や年間・個別研修計画、研修テーマの例、研修資料の作成方法と注意点を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
目次
- 訪問介護で実施しなければならない「法定研修」とは?
- 訪問介護の年間研修計画・個別研修計画とは?
- 訪問介護における研修テーマの例【21選】
- 訪問介護の研修資料を作成する方法は?
- 研修用の資料を作成する際のポイント
- まとめ
訪問介護で実施しなければならない「法定研修」とは?
訪問介護の「法定研修」とは運営基準で実施が義務付けられている研修のことです。
運営基準の第30条には「事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。」と記載されています。
つまり、介護業務に係る研修など、幅広い範囲で『資質向上のための研修』を実施しなければならないということです。
「訪問介護の法定研修」について詳しくはこちらの記事をご覧ください]
訪問介護の年間研修計画・個別研修計画とは?
訪問介護において研修を実施するためには、しっかりと計画を立てることが大切です。
研修計画には、主に「年間研修計画」「個別研修計画」の2種類があります。
年間研修計画とは、事業所がその年度に実施する研修の計画書です。
運営指導の確認文書には「研修の計画及び実績がわかるもの」が定められており、「年間研修計画」の作成は義務になっています。
個別研修計画とは、職員ごとのその年度に受講する研修の計画書です。
訪問介護事業所が特定事業所加算を算定する場合は、「個別研修計画」が必要になります。
訪問介護における研修テーマの例【21選】
ここでは、訪問介護の研修テーマの例をご紹介します。
接遇・マナー研修
利用者様やご家族との信頼関係を築くための言葉遣いや態度、服装や身だしなみなどの基本を学びます。
訪問介護では利用者様のご自宅に入るため、プライバシーへの配慮や家の中での立ち振る舞いを身に付けることも重要なポイントです。
移乗技術についての研修
ボディメカニクスを活用し、利用者様とヘルパー双方の身体への負担を減らす技術を学びます。
ボディメカニクスとは、身体の構造や力学を活用して最小限の力で効率的かつ安全に動作するための介助技術です。
8つの原則を踏まえ、実践を交えながらスキルを身に付けるとよいでしょう。
福祉用具の使い方研修
福祉用具を正しく安全に使用するための知識を学びます。
正しい使用方法だけでなく、利用者様の状態や体格に合わせた用具の選定・調整方法を習得することで、事故を防止します。
メーカーの仕様書や実物を用いた実践形式で行うと良いでしょう。
排泄ケア研修
おむつ交換やトイレ誘導、陰部洗浄などの排泄ケアに関する基本技術を習得します。
利用者様の尊厳を守りながら、皮膚トラブルを予防する方法や姿勢保持、おむつ交換、洗浄など排泄介助の方法を学びます。
安全な入浴介助の研修
事故を未然に防ぎ、安全に入浴いただくための知識と技術を学びます。
次のような内容を身に付けられるような研修にすると良いでしょう。
- 入浴前後の体調チェックの方法
- 入浴介助用具の使い方
- ヒートショック対策
- 身体を洗う順番
誤嚥防止・食事介助の研修
安全な食事姿勢や、利用者様に合わせた食事介助方法を学びます。
スプーンの使い方、ひと口の量、声かけのタイミングなどの食事介助のポイントに加え、誤嚥時の対処法や基礎知識を身に付けます。
調理研修
高齢者に適した栄養バランスと食べやすさを考えた調理スキルを習得します。
嚥下しやすい調理方法や減塩メニュー、持病に応じた食材選びや現場での短時間調理の工夫を学びます。
認知症ケアの基礎研修
認知症の症状や対応方法を理解し、適切なコミュニケーション方法を学びます。
認知症の基礎知識や現場で起こりやすい行動への対応方法、家族支援のポイントも含めて習得します。
コンプライアンス研修
訪問介護におけるコンプライアンス(法令遵守)の重要性を再確認します。
遵守すべき法律、運営基準、個人情報保護や虐待防止などを学びます。
次のようなトピックが主な学習の内容になります。
- コンプライアンスの概要
- 遵守すべき法律や規制、ルール等
- コンプライアンス違反の事例
- 違反が起きた場合の対応
- 内部通報制度
ターミナルケア(看取り)研修
人生の最終段階にある利用者様への心身のケアやご家族への支援を学びます。
看取り経験のある職員に実際の経験を交えて解説してもらうのも良いでしょう。
服薬介助についての研修
訪問介護員ができる服薬介助とできない行為の区別、服薬忘れ防止や安全管理を学びます。
医療職との連携方法も学習します。
口腔ケアについての研修
歯磨きや義歯清掃など、誤嚥性肺炎予防や口腔機能の維持を目的としたケアを習得します。
口腔状態の観察ポイントや歯科との連携についても学びます。
緊急時対応と救命措置
利用者様の急変時に落ち着いて対応できるよう、救急要請の流れやAEDの使用方法を実技で学びます。
バイタルの異常や転倒など、よくある緊急事態の学習もします。
傾聴・共感スキル研修
傾聴・共感スキルを高めて利用者様の思いに寄り添い、信頼関係を深めるためのコミュニケーション技術を学びます。
「聴く」だけではなく、表情や相づちや言葉などによる「共感」を通して関係性を深める力を養います。
職員同士によるロールプレイ形式で実践するとより効果的です。
アサーティブコミュニケーション研修
相手を尊重しつつ、自分の意見や要望を率直に伝える方法を学びます。
職場や利用者様・ご家族との円滑な関係構築に役立ちます。
メンタルヘルスケア研修
職員自身のストレスや感情コントロールの方法を学びます。
燃え尽き症候群の予防やセルフケア、相談窓口の活用など、心の健康維持を目的とします。
クレーム対応の研修
クレームの背景にある思いを理解し、誠実に対応する方法を学びます。
感情的なやり取りを避け、迅速かつ適切に対応するスキルを身につけます。
介護記録の書き方研修
介護記録の目的やポイントを理解し、適切な記録が書けるように学びます。
介護記録は、利用者様の健康状態の把握や、運営基準の遵守にも直結するため、具体例を交えて正しい記入方法を習得します。
介護保険制度についての研修
介護保険の仕組みや、制度改正のポイントを学びます。
制度理解は、適切なサービス提供や健全な事業所運営にも繋がるでしょう。
リスクマネジメント研修
事故を未然に防ぐための危険予知や対策について学びます。
ヒヤリ・ハット事例の共有も有効です。
キャリアアップ研修
介護業界の資格取得やスキルアップについて学びます。
介護福祉士やサービス提供責任者など、将来のキャリアアップについて考える機会になるようにしましょう。
ハラスメントについての研修
職場やサービス提供現場でのパワハラ・セクハラ・カスハラを防ぐための知識と対応方法を学びます。
事例研究や適切な相談ルートの理解も含めて学習します。
訪問介護の研修資料を作成する方法は?
訪問介護で研修資料を作成する手順を、4つのステップで解説します。
Step1.テーマを選定する
まずは、研修のテーマを選定するために事業所の課題を洗い出します。
管理者の視点だけではなく、職員にヒアリングして課題を洗い出すと良いでしょう。
課題が明確になったら、その解決に繋がるテーマを選びます。
例えば、入浴介助に不安を抱えている職員が多数いる場合は、「安全な入浴介助」をテーマに設定します。
Step2.情報収集
選定したテーマについて、スタートとゴールを決めます。
そして、ゴールするまでに必要なトピック、知識、スキルなどについて情報を集めます。
Step3.構成の決定
集めた情報を、聞き手が理解しやすい順番に並べ替え構成を作ります。
構成は「序論・本論・結論」の流れを基本にすると作成がスムーズです。
Step4.PowerPointやGoogleスライドで資料を作成
最後に、組み立てた構成をもとにPowerPointやGoogleスライドで研修資料を作成します。
資料の基本的な構成要素は次の通りです。
【基本的な構成要素】
- 表紙: 研修タイトル、日付、対象者、法人・事業所名など
- はじめに: 研修の目的、ゴール、アジェンダ
- 本編: 構成に沿った各スライド
- まとめ: 重要なポイントの振り返り
- 質疑応答 ・ 今後の案内
研修用の資料を作成する際のポイント
研修用の資料を作成する際は次の点を意識しましょう。
1スライド1メッセージ
1枚のスライドには多くの情報を詰め込まず、伝えたいことを一つに絞りましょう。
情報が多すぎると、「何を伝えたいのか」がわかりづらくなってしまいます。
1スライド1メッセージにすることで、受講者がスムーズに理解しやすくなります。
結論から書く
各スライドのタイトルには、そのスライドで伝えたい結論(メッセージ)を入れましょう。
はじめに結論を伝えることで、続く内容が理解しやすくなります。
文字を詰め込みすぎない
文章での説明を詰め込みすぎず、図・グラフ・イラスト・写真などを効果的に使いましょう。
視覚情報を活用することで、内容を直感的に理解しやすくなります。
デザインを統一する
フォントの種類やサイズ、色の使い方などのルールを決め、全体に一貫性を持たせた資料になるよう心掛けましょう。
デザインに統一性がないと集中が途切れたり、読みにくい資料になってしまいます。
まとめ
この記事では、訪問介護の法定研修や年間・個別研修計画についてや、研修テーマの例、研修資料の作成方法と注意点を解説してきました。
訪問介護では運営基準で研修の実施が義務付けられています(法定研修)。
事業所で研修テーマを選ぶ際は、漠然と決めるのではなく、事業所の課題や目標に合わせてテーマを設定しましょう。
また、適切に研修を実施するためには、年間研修計画・個別研修計画でしっかりと計画を立てることが大切です。
法定研修や年間研修計画・個別研修計画について詳しく解説した資料をダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
事業所運営に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト