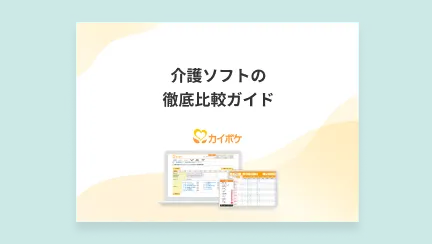介護記録の電子化のメリットと導入の流れをご紹介!
介護業界では今、生産性向上が急務となっています。
「忙しくて利用者様に対するケアの時間を確保できない」「記録業務に時間が掛かっている」といった状況に悩まれている方も多いのではないでしょうか。
このような課題の要因として「紙の介護記録を作成していて、転記に時間がかかっている」という場合があり、解決する手段のひとつとして「介護記録の電子化」が挙げられます。
しかし、導入を検討するなかで、「具体的にどんなメリットや効果があるの?」「どうやって電子化を進めればいいの?」など、様々な疑問や不安が発生するかと思います。
そこでこの記事では、介護記録の電子化の基礎知識から、メリット・デメリット、導入の流れ、導入事例について詳しく説明していきます。
目次
介護記録の電子化とは?
介護記録の電子化とは、これまで紙に手書きで記載していた介護記録を、パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデジタル端末を用いて、データで入力・保管することを指します。
記録業務がペーパーレス化されるだけでなく、スムーズな情報共有、データの活用、保管スペースの節約など、様々な面で効率化が図れます。
人手不足と事務業務負担への対策や、科学的介護への対応、2024年度介護報酬改定における生産性向上の推奨といった観点からも、介護記録の電子化は急務と言えるでしょう。
介護記録を電子化するメリットと効果
介護記録の電子化のメリット
介護記録を電子化するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 入力や修正が簡単になり、記録業務にかかる時間が削減できる
- いつでも・どこでも記録ができる
- 情報共有がスムーズになる
- 紙の記録が不要となり、印刷代や紙代のコストを削減できる
- ファイリングなどの書類管理の手間を削減できる
- 業務効率化により残業・人件費を削減できる
- 紙の紛失リスクがなくなり、災害時の対策にも繋がる
介護記録の電子化の実際の効果
厚生労働省「ICT導入支援事業 令和3年度 導入効果報告取りまとめ」を参考に、ICTを導入して介護記録を電子化した事業所の導入効果をご紹介します。
文書作成や情報共有の業務を効率化
ICTを導入した事業所の多くが、業務効率化と情報共有の円滑化を実感しています。
特に回答が多かったのは、以下のような項目でした。
- 情報共有がしやすくなった…90.3%
- 入力済みの情報を他の文書でも利用できるようになった(転記作業の削減)…84.8%
- 文書作成の時間が短くなった…81.9%
- 支援の質の向上に活かせるようになった…75.6%
- ファイリングの時間が減った…75.3%
その他、介護記録に関する回答として「記入ミスが減った」という意見も挙がっています。
間接業務時間を削減し、直接業務時間が増加
7割以上の事業所が間接業務時間を削減できたと回答し、確保できた時間は、主に以下のような業務に活用されています。(数値は導入1年目の回答)
- 利用者とコミュニケーションする時間…52.0%
- 利用者の直接ケアの時間…45.0%
- 職員間でコミュニケーションする時間…39.1%
- 職員の残業時間の削減…39.8%
このように、介護記録の電子化は、ペーパーレス化だけに留まらず、業務効率化によって確保できた時間をケアの質の向上や職員の負担軽減に活用することを可能にし、事業所全体の運営を改善することにも繋がる重要な取り組みと言えます。
介護記録の電子化で注意すべきデメリットと対策
実際に介護記録の電子化を進める際には、様々な課題が発生する可能性があります。
そのなかでも特に注意しておきたい、3つのデメリットと対策を詳しく見ていきましょう。
①導入コストがかかる
介護記録の電子化を進めるためには、パソコン、スマートフォン、タブレットなどのハードウェアや、介護ソフトなどのソフトウェア、Wi-Fi環境やインターネット環境を導入・整備することが必要になります。
そのため、どうしても導入時の初期費用やランニングコストが発生します。
対策としては、補助金や助成金の活用がおすすめです。
厚生労働省はICT導入を推進するため、補助金や助成金の制度を設けています。
補助金・助成金の対象になると導入費用やランニングコストの一部を助成してもらえるので、対象になるかどうかを確認しましょう。
②教育の必要がある
介護記録を電子化して業務効率化を実現するためには、導入したICTツールを職員に活用してもらう必要があります。
せっかく最新のICTツールを導入したのに、職員に使ってもらえなかったり、使いこなせなかったりすると、良い効果が得られません。
対策としては、ICTに関する研修や勉強会の開催や、マニュアルの作成などが考えられます。
特に、使い方やルールなどを記載したマニュアルを作成することで、誰でも同じような使い方ができ、教育コストの削減にもつながります。
職員のなかには、スマートフォンやタブレットなどのICTツールの操作に苦手意識が強い方もいるかもしれないので、その場合は丁寧にフォローしましょう。
③社内の業務手順(オペレーション)を整備する人材が不足している
介護記録の電子化を進めるためには、ICT機器を活用した新しい業務手順(オペレーション)を構築できる人材が必要です。
記録業務だけでなく、導入したICTを活用できるオペレーションを構築するには、ICTツールに対する理解と現場の業務についての理解があり、効率化を進めつつ、発生する問題を解決できる人材が求められることになります。
対策としては、ICTに精通した人材の採用や、社内の人材育成が考えられます。
どちらも困難な場合は、外部の専門家に依頼したり、介護ソフトやICT機器の販売会社に協力を要請したりする方法もあります。
ただし、外部に依頼する場合は、現場の意向に沿った導入ができるように意思決定を行うようにしましょう。
介護記録の電子化の流れ
介護記録の電子化をスムーズに進めるため、参考となるICT導入の流れをご紹介します。
厚生労働省の「介護事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き」によると、導入プロセスは7ステップに分けられます。
- 導入計画の作成
- 導入するICTの検討
- ICT導入に伴う業務フローの見直し
- ICT導入の際の実施体制を整備
- ICT導入に係る関係者への説明等
- ICT導入に関する職員への研修
- ICT導入の効果を検証
各ステップの詳細はこちらのページをご覧ください。
介護記録の電子化の導入事例3選
事例1:ライジングサン株式会社 様
膨大な紙業務がPC1台で完結!業務効率化を叶えるカイポケ活用術
課題:
- 記録用紙(テレッサ)の確認、実績への転記に膨大な時間がかかる
- 年間約35,000枚の記録用紙(利用者1人月70~80枚×12ヶ月×38名)の管理、保管が大変
- 机が紙でいっぱいになるほど紙の業務が多く、ファイリングなど煩雑な作業が発生
効果:
- 記録や帳票などのチェックはPC1台あれば完結、ペーパーレス化
- データ連携が浸透し、FAX業務も削減
- 運営指導対策など間接業務の効率化を実感
詳細はこちらのページをご覧ください。
事例2:社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 様
請求業務が月30時間減!|社会福祉法人が運営するデイサービスでのカイポケ活用
課題:
- 利用者の出欠やサービス内容の記録、連絡帳を手書きで作成しており転記作業が多い
- 記録を確認しながら行うため、提供票に「実績の1立て」をする業務に膨大な時間がかかる
- 毎月の請求業務に5日かかり、2人で1日3時間、計30時間の残業が発生
効果:
- 転記作業や連絡帳の作成など間接業務が減り、利用者に関わる時間が1日1時間増えた
- 請求業務は2日で終わる!作業も1人で日中2時間程度に短縮し、1人15時間の残業が削減
- タブレットを担当者会議に持参し、家族やケアマネに利用者の様子を具体的に伝えられる
詳細はこちらのページをご覧ください。
事例3:社会福祉法人ワゲン福祉会 様
75歳のヘルパーもスマホ記録を活用!ICT化で様々な業務が効率化
課題:
- 通所も訪問介護も手書きで記録しているためにチェックや転記に時間がかかる
- 請求に使っていたソフトは記録機能がオプション扱いで予算外
効果:
- 通所介護‐タブレットの活用で20人分の記録が約30分で完結、 利用者との関り増
- 訪問介護‐75歳のヘルパーもスマホ記録を活用、指示・連絡のやり取りが効率化、特定事業所加算の算定条件をクリア
- 事務員‐ICT化でシフト調整、記録確認、請求業務が効率化
詳細はこちらのページをご覧ください。
まとめ
ここまで、介護記録の電子化について詳しく説明してきましたが、いかがでしたか?
介護記録の電子化によって業務効率化を図ることができ、確保した時間をケアの時間に充てることで、ケアの質の向上が期待できます。
しかし、導入コストや職員の教育、社内オペレーションを整備できる人材の確保といった課題・デメリットもあるため、導入前に予算や導入手順をしっかりと把握し、効率的に進めることが重要となります。
介護記録の電子化を進めたいと考えている方には、記録・請求まで一気通貫で行える介護ソフト『カイポケ』がオススメです。
コストパフォーマンスの高さと使いやすさから評価を受け、多くの介護事業所にご導入いただいておりますので、ぜひご検討ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ソフト比較に関する資料を無料ダウンロード
はじめやすく、
ずっと使える介護ソフト